夏になると落葉広葉樹の林も林床はすっかり暗くなってしまいます。花をつける植物も少なくなってしまいますが、シダ植物の観察には絶好の季節となります。
木漏れ日のもれる林道を歩いていてまず見られるのがヒカゲノカズラ科ではこれらです。
 |
 |
| ヒカゲノカズラ |
アスヒカズラ |
ヒカゲノカズラは少し乾いた場所に普通に見られます。夏にはこのように胞子穂を伸ばし、少し揺すってやると胞子が一杯飛び散ります。アスヒカズラは冷温帯性のシダでこのような低標高地で見るとは少し驚きました。1000mぐらいの場所で所々で観察することができます。
 |
 |
| ハリガネワラビ |
ヘビノネゴザ |
ヘビノネゴザは少し湿った日陰に、ハリガネワラビは少し乾いた日陰で普通に見ることができます。食べられるシダとして有名なワラビやクサソテツも普通に見ることができます。ワラビはあく抜きに工夫が要りますが、クサソテツはそのままお浸しで食べることができますので便利です。しかし葉の成長が速いためちょうど良い時期に出会うには運も必要です。
 |
 |
| マンネンスギ |
シシガシラ |
コナラ、ミズナラを中心とした林では林床が乾いていたり、ササに覆われていたりでシダはあまり見ることができません。この2種類が代表的なものです。
しかし当地では谷沿いなどにスギの植林地が拡がっているためにそこではかなりの種類のシダを見ることができます。
オシダは冷温帯を代表するシダであちこちで群落をつくり最も普通に見られる種類です。国内にはイノデの仲間がたくさん知られていますが、当地で普通に見られるのはこのサカゲイノデで他の種類はほとんど見られません。荘川村ではホソイノデやイワシロイノデも見られますがそんなに多いものではありません。
シノブカグマ、シラネワラビも普通に見られ、その他にトウゲシバ(ホソバトウゲシバの型)、サトメシダ、リョウメンシダ、ジュウモンジシダ、ヤマイヌワラビなども普通に見ることができます。
当地では雑種のシダとしてオオサトメシダ(割合多い)、タカヤマナライシダ(少ない)も見ることができました。
 |
 |
| ウバユリ |
コオニユリ |
町屋地区で見られる夏の代表的な花です。ウバユリは林床のやや湿った場所で普通に見られます。この個体はたいへん花付きの良いものですが、一般には数輪のものが多いようです。
ウバユリは照葉樹林帯上部から冷温帯にかけて普通に見られるのですが、ウバユリとオオウバユリとを区別することには少し無理を感じます。両者は葉の形や花数などで区別されていますが変異は連続的で北にいくほど大型化して花数が多くなる傾向があります。これまでも中部地方の各地から東北地方・北海道にかけてかなりの個体を観察しましたが、そんな気がしてなりません。
コオニユリは山裾や水田の畦などで見かけます。この画像では右下にヒメシダが写っていますが、両者はどうも相性が良いようです。
荘川村ではユリの仲間ではこのコオニユリとササユリの2種類が見られますが、ササユリは最近激減したように思います。原因は盗掘だろうと思います。
町屋地区でもつい最近まであちこちで見ることができました。私の山小屋の庭でも自生しており、その個体から種子を採って下草刈をしながら繁殖に努め、かなりの群落にすることができましたが、そのほとんどが盗掘にあってしまいました。毎年10数株が開花していたのですが、今年(2004年)は花を着けない小さな株が一株のみ残っています。この春には多数の発芽を観察していたのにです。
ササユリは球根の移植が難しく、そのほとんどはウイルスに罹ってしまい駄目になります。そのため露地での実生栽培でしか健全な生育はほとんど期待できないのです。花泥棒は決して優雅なものではないと思います。
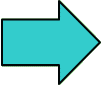 トップページに戻る
トップページに戻る














トップページに戻る