明日の資料(2011.7.22)
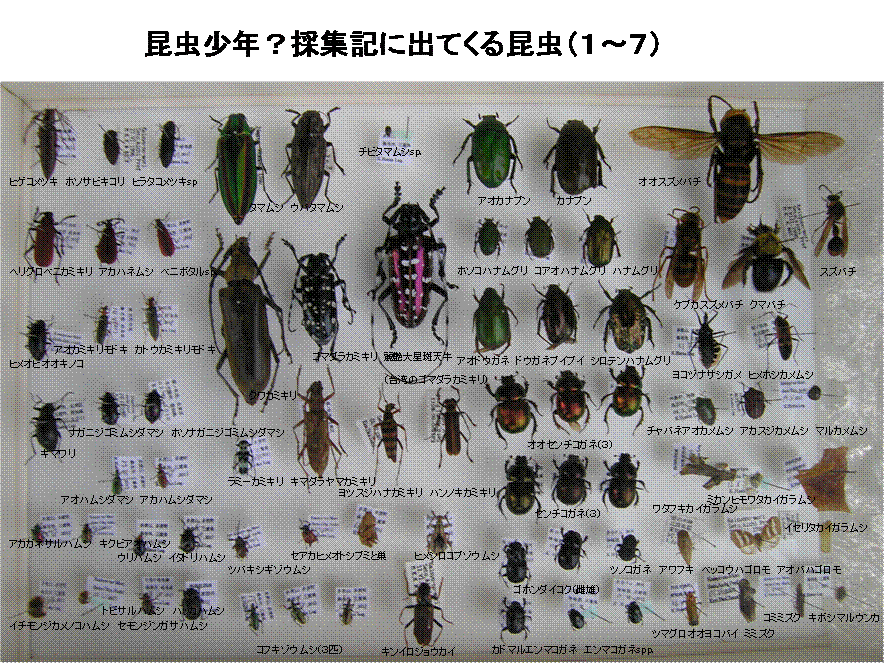
上田さん 八田です(2011.7.19)
アケビコノハの幼虫、グロテスクなのを見つけましたね。
成虫はきれいなので、人気のある蛾ですが、最近ほとんど見れないので、是非飼育してみる ことをお勧めします。
写真から見ると、ほぼ終令なので餌となる食草(アケビ、ムベ、ヒイラギナンテン、アオ ツズラフジ)も一緒に持って変えると、すぐに葉を綴った粗い繭を作るでしょう。
私も、アサガオやブドウ、サツマイモにつくスズメガの幼虫をいくつか飼育しています。 終令幼虫を探せば、簡単に蛹になります。ただしこの仲間は土にもぐって蛹になります(土蛹 )。大型のガはなかなか魅力的ですが、鱗粉の落ちていない完全品はなかなか取れないので、 是非お勧め。同様に採集しにくいトンボ類の幼虫採集もお勧め。
どんどん昆虫の魔力に引き込まれていくのを想像して、ニヤニヤしているジイジイより。
上田♂です。
八田先生ありがとうございました。
ド素人の同定では不安いっぱいなので、先生の一言がとってもありがたいです。
23日を楽しみにしています。
添付の写真は何?と思う人が多いと思いますが、アケビコノハと言うガの幼虫です。
会いたかったイモムシの一つです。
上田さん 八田です。(2011.7.19)
海上の森には、14日に歩いてきました。いつも私は、吉田川から赤池経由で、屋戸の湿地に 行きます。
残念ながら、今回はクワカミキリの馬鹿でかいのを採ったぐらいで、ウラギンシジミをたくさん 見かけたぐらいです。18日にも多度に出かけてきまし たが、端境期なのかさっぱりでした。
上田さんのメールうらやましく読ませてもらいました。今度行くときには、コースを変えてみ ます。面白そうなところをお教えください。
オオセンチとセンチの違いは、一見して光り方が違うので、細かい特徴は無視しています。強いて 言えばオオセンチのほうが前胸背がやや横に広く、中央の縦溝が長く、前方に達しており、センチ コガネのほうがやや小さく、丸くて、縦溝は後方に少しあるぐらいで、ほとんど見えないぐらいで す。この ことから察して、センチコガネのようです。
実物を見たら、はっきり解ると思いますので、23日の酒の肴に持って行きます。
八田先生、皆さんこんにちは上田♂です。
昨日も海上の森に行って来ました。
最近は虫の報告ばかりになりますが、雨が降りだすといけないので、とりあえず虫のレストランに 行ってみるとノコギリクワガタ♂・♀、ヨツボシケシキスイ、キマワリ、ヒカゲチョウが食事中で した。
サテライトを往復したのですが道端でタマムシ2匹、ノコギリカミキリ、アケビコノハの幼虫、 コクワガタ♀、センチコガネ等を見る事ができました。
今までインターネットで調べていたのですが前胸背の真ん中に筋が入ってないし頭の形も丸そうな のでオオセンチコガネではないと思いますが、いかがでしょう?
写真を撮ろうと思っても走り回ってなかなか止まってくれなくて、こんな写真しかありませんが ・・・。
センチコガネを漢字で書くと雪隠黄金は、なるほどと感心しました。
昆虫少年?虫捕り記7(2011.7.19)
上田さんの昆虫採集記を見て、久しぶりに書きます。
虫捕り記6以来、多度・養老線、記念公園・海上の森コースなどに行ってきましたが、今回は
塚のいり池を書きます。
名古屋市がCOP10がらみの「ため池協議会」というCOP10協賛団体による外来種駆除のため、ため池の池干しを3年ほど前からやっています。 今年度は10月に名東区の猪高緑地にある塚のいり池の池の水を抜くため、池の中央に道路をひく計画が出ています。池の中央に車両が通る道路を造るという暴挙も、市民参加型との名目で影響調査もなく、堂々と行われるのも万博やCOP10効果なのでしょうか。
池干しは、水質浄化や外来種駆除のために最近見直されていますが、在来種、特に水草などの希少種保護の立場から異論も出ています。私が所属している「ため池の自然研究会」でも、協議会と間違われて意見、質問が寄せられるようになり、研究会としても池干しの是非、影響・効果についてきちんと科学的に立証する必要性があると考え、昨年9月からきちんと調査をすることになりました。
前置きが長くなりましたが、毎月1回ではあるが昆虫の調査をしています。もちろん、水質、プランクトン、水草等の調査も研究会のメンバーで行っています。今月は11日に夜間採集(昨年の8月より月1で)をしました。夕方(日没前)から行うため、午後からは名東区の高崎保郎さん(私のトンボ の師匠)と愛知学院大学の構内にある池にベニイトトンボ(絶滅危惧種、II類)を見に行きました。以前は愛知工業大学の構内の池にも行きました が、まだまだ長久手、日進には自然が残っているようです。
さて、本題の樹液採集ですが、池の周りの樹液めぐりをするとコクワガタ、カナブン、キマワリ、オオスズメバチの大宴会に出くわしました。キマワリは大きな木の幹の周りを長い足で、急いで木の後ろ側に隠れるので、海上の森でも良く見られると思います。オオスズメバチに恐れをなして、その場を離れようとしたところぴかぴか光る個体に目が釘付けに。なんと久しぶりのアオカナブンではないですか。そこで、恐る恐るまずはオオスズメバチをゲット、もちろん刺されないようにおっかなびっくり、へっぴり腰で。アオカナブンが逃げることを心配していましたが、カナブンたちは大宴会で大騒ぎ中、誰かさんのようにブイブイ言いながら、酩酊中。
アオカナブンとカナブンとの違いは、後ろ足(後肢)の付け根がくっついているかどうかで見分けられますが、あの輝きは絶品です。そのすばらしい輝きに、昔の昆虫少年は王様ブイブイとも読んでいました。
私はクワガタムシの成虫が出る7月までは、朽木採集をムシの採れない時期の楽しみの一つにしています。池の周りはコナラ等の立ち枯れや切り倒された木が輪切りにされて放置されており、良い状態で朽ちている木を探しナタで割ると、カブトムシより小さな白い幼虫が出ます。海上の森も輪切りされた木 が転がっていますが、多くは白い薬をまぶされビニールでまかれているさまは何か異様な感じがします。森や木を管理している人にとっては、森や自然 の危機と大変な状況と考えているのでしょうが、私個人としては自然の撹乱・遷移だと思っています。山や自然が洪水や地震によって壊されても、長い自然の遷移の中で、回復するのには思っているほど長い時間はかからないと思います。いろんな遷移の段階を持つことにより、生物の多様性が増すということは古くから知られた生物屋さんの常識なのですが。撹乱・遷移と外来種・池干しについては、他のところで考える機会を設けましょう。
夜間採集は、トビケラの野崎隆夫さん(元神奈川県環境科学研究所)http://homepage2.nifty.com/tobikera/とユスリカの近藤繁生(愛知医大)さんを中心にライトトラップ(灯火採集)をしました。残念ながら、今回は時期が悪かった(羽化の端境期)せいか、トビケラやユスリカなどの水生昆虫の羽化は少なかった。しかし、私の好きなコガネムシがアオドウガネ、ドガネブイブイ、クリイロコガネ、クロコガネ、スジコガネ、オオスジコガネ、セマダラコガネ、コフキコガネが飛来し、コクワガタやカナブン、アオカナブンなどが樹液に来るなど久しぶり の夜間採集を満喫しました。アオドウガネは最近温暖化の影響を受けたのか日本列島の南部から北上し、名古屋でも大発生していましたが、もともとこの地域にはドウガネブイブイが広葉樹の葉を食害し、街燈に飛んでくるので嫌われていました。パンジーなどのスミレを食するツマグロヒョウモンとともに、温暖化の指標ともなっています。アオドウガネも定着したのか、最近見られることも少なくなってきました。
27日より8月3日までは、台湾で甲虫を主体とした昆虫採集に出かけます。今回は、まったくのプライベートな昆虫採集なので、中興大学の楊曼妙先 生のところの学生さんにレンターカーを借りて運転をしてもらい、台中市周辺の採集地に行く予定です。次回には、報告できると思います。楽しみに。

アオカナブンとカナブン

オオスズメバチ(女王)
こんにちは上田♂です。
鳥は諦めてコナラ等の樹液の出ている樹を探して歩くとコクワガタやヨツボシケシキスイ、
カナブン、オオスズメバチを見る事ができました。
に身を置こうと海上へ行って来ました。
サテライトでお昼を食べていると高いところを3〜4匹のタマムシが飛んでいました。
タマムシもオオムラサキの幼虫も食草はエノキなので、近くに生えているのかも。
サテライトでオオムラサキを見たのも、ちょっと納得できました。
海上は、いつ行っても楽しいですねぇ。
上田さんへ 八田です
とりあえず手持ちの図鑑にあるもので、ニジゴミムシダマシとしてよいかと思います。
ニジゴミムシダマシ(5ミリから10ミリ以下)のグループは、ナガニジゴミムシダマシ (10ミリ〜13ミリ)のグループより小さく、上翅の条溝(細い溝のようなすじ)と全形、 前胸背の形からすれば、ナガのようです。
私の手持ちの標本で、ナガとしましたが、写真から見て全体の形から見るとニジよりも長く感じ ます。
今後、採集していくうちに、よく似たものが現れてくるので、実物で比較すると一目瞭然でわかる と思います こんにちは上田♂です。
八田先生、お手間を取らせた上に、色々アドバイスをいただきありがとうございます。残念ながら僕の図鑑にはニジゴミムシダマシしか載っていませんでした。本種でない事はわかったので他をネットで調べていたのですがナガニジとホソナガの違いを明記 したページがなく結局わからず終いでした。 が、素人の危険な感からすると先生の言うようにナガニジゴミムシダマシかな?っと思っていま す。 私の手持ちの図鑑にも記載がないのですが、傷ではなく、明らかにこの種の仲間の特徴で、私の 標本(1個体のみ)でもあります。多分この科の検索表 (一つ下のグループ、ここでは属に分け ていくときの区別点)か、原記載(新種と記載)にはこの属の特徴として書かれていると思います?。
写真の個体もそうですが、ネットで見たナガニジゴミムシダマシの前胸背(こんな単語を使うよう になりました)が皆ヘコミがあったのですが、ただの脱皮する時のキズですか?
同定(2001.6.27)
昆虫採集記の話を書いてきて、少し興味を持ってくれる人が出てくること期待して、上田さんの質問に
お答えします。
昆虫の種名の決定(同定)のポイントを、本に載っていない正統派でない、私のやり方を紹介します。
あまり、他人には教えないでください。異論があることが多いし、人づてで伝わると誤解を生むことも
あると思います。そのような場合には、私が説明、あるいは補足をすることも出来ません。あくまで、
私の持論ということでご承知ください。
まずは、図鑑の写真で似ているものを探す絵合わせを多くの本では否定されていますが、はじめのうち はそれで十分です。ただ、その標本を後で見比べると多くの間違いに気づきます。まずは、興味を持つ ことの一つは、その虫に名前をつけることが優先します。いくら調べても、名前が確定できないことは 興味を半減させます。植物の観察でも、そうなんですが他人に名前を教えてもらってもすぐに忘れます。 小さな子供が図鑑、昆虫だけでなく、恐竜、乗り物などの図鑑を何度も何度も見ることにより、知らぬ 間に名前を覚えているのをまねしましょう。 次に具体的な種名の決定を述べましょう。まずは、大きさ、色、形、すなわち絵合わせです。図鑑を見る ときに気をつけねばならないのは、虫の大きさ(縮尺)など、記載文(説明)を読むことです。はじめは 難しい内容ですが、わからないところは読み飛ばして結構です。そのうちに、どこの部分が重要なのかは 徐々にわかってきます。最初は、大きさ、色、分布地域(たとえば、沖縄や北海道にしかいないのは、 最初から除外)、生息域(採集した環境が平地なのか、山地なのか、海浜、草地など)、採集場所 (花上、葉上、地上、寄主植物)の情報が正しいか確認。よく似たムシが何種類かいても、大きさ、 産地などをはずしていくことだけでも絞れてきます。
最初は、大きなグループの特徴を把握すること。そのために、何度も何度も図鑑を見ていると、まったく
違ったページからも良く似た虫が見つかることで、各グループの特徴がおのずからボヤーッと見えてきま
す。カミキリとカキリモドキやジョウカイボン、ホタルとベニボタルやベニカミキリなど良く似た形をし
ていても、そのうちにそれぞれのグループの違いがわかるようになります。たとえば、触角の形、翅の形
などに大きな特徴があります。
細かい種名の決定は、私は直感的に違いがわかる程度でないのは無視しています。多くの標本をそれぞれ
並べていくうちに、ちょっとおかしいなと気づくようになります。それまでは、邪道ですが、普通種と
記載しているもの(まれと欠かれているものは除く)、産地、採集場所の特殊なものは除くだけでも、
かなり正確になります。ここで大事なことは、実物で比べるということです。多くの昆虫採集家は、この
ために採集、標本にこだわるのです。ただし、この理屈で同じムシ、たとえばギフチョウなどを標本箱に
いっぱい並べているのは、ただの収集癖でマニアと称する人たちの詭弁です。私は、せいぜい同じムシを
採るのも数匹程度でよいし、大きいのにこだわるのはまさに収集癖の典型です。なぜなら、自然界には、
オオクワガタのギネスは存在しません。
採集是非論が議論されて、小学校の自由研究から昆虫採集や植物標本が消えてしまったためか、大学にも
昔のような自然系のクラブや研究がほとんど見られなくなったのと相反して、最近の自然観察会ブームも
かつての少年、少女が目覚めてきたためでしょうか。老年・中年(どちらかな)パワー万歳。
こんにちは上田♂です。
昨日は仕事から逃げられず観察会に参加できなかったので、今日海上に行って来ました。
みなさんに残念なお知らせをしなければいけません。先週MLで流した写真のサンコウチョウは巣作りをやめてしまいました。その道の奥で営巣中(すでに抱卵中で後2・3日で孵化するのでは・・・と思われていた)だった巣は放棄してしまいました。連日、巣の下で長時間見ている二人の人がいたという情報もあります。そのことが巣を放棄した直接の原因になったかどうかはわかりませんが、少なくとも思いやりのある行動とは思えません。謙虚な気持を忘れずにいたいものです。
話は変わりますがGWの段戸以来、八田先生に感化されて、今年から虫も力を入れてみようとしゃがみこんでいます。
けっこうかわいいマルカメムシやキツイ顔してるからゴミムシの仲間かと思ったらヨツスジハナカミキリだったり初心者なりに楽しんでいますが、今日虹色に光るキレイな虫を見つけて写真を撮ったのですが識別ポイントもわからず撮って来るのでよくわかりません。
八田先生こんな写真でわかりますか?

八田です。
写真では大きさがわからないのですが、多分ニジゴミムシダマシかオオニジゴミムシダマシ、また はナガニジゴミムシダマシかホソナガニジゴミムシダマシのようです。
この二つのグループはそれぞれ数種いますが、この二つのグループの大きな違いは上翅の縦の点刻 列がポイントです。図鑑があれば見比べてください。 多分ナガニジゴミムシダマシのようです。 私も記念公園で4月に1頭採集しました。
ゴミムシダマシはゴミムシに似ているようなものもいますが、ハムシに似たものや足の長いキマワリ など、日本では300種を越すグループです。
昆虫少年?虫捕り記6(2011.6.25)
先週の金・土(17,18日)に、高校時代の生物部の先輩の山の家に行ってきました。
今回の昆虫少年たち(私を含んで4名)の採集目的は、村上春樹の「ノルウェーの森」のロケ地である兵庫県神河町の砥峰(とのみね)高原の近くのダムなどで、オオセンチコガネやゴホンダイコクなどの動物の糞を食べる糞虫と呼ばれる虫の採集です。
最近、どこの山でも野生の動物が増え、イノシシ、サル、シカの被害が良く聞かれるが、虫捕り屋さんにとってはありがたいことです。先輩の別荘の菜園にもサルよけネットが張られ、被害が多く、出来るだけとられないものを植えなければと言っていました。鈴鹿山系をはじめ、東海地方ではヤマビルが増えて、沢筋の登山は控えていましたが、今年は多度山の山歩きをはじめたところオオセンチコガネ(前回紹介のぴかぴか のコガネムシ)が毎回2〜3匹採れ、大変楽しい山歩きになりました。幸いイノシシには出会うことはなかったが、サルとシカには良く出会い、遠めに 最近変なおっさんが出没すると見られているようです。
ついでにもう一つムシ屋さんの独り言。カシノナガキクイムシ(カシナガ)が媒介するナラ菌によるミズナラ等が集団的に枯損する「ナラ枯れ」により、東海地方のミズナラ、コナラなどのブナ科の立ち枯れが目立つようになるなど問題となっているが、朽木にはクワガタムシなどのコガネムシの幼虫が多産するという、不謹慎ではあるがムシ屋にとっては喜ばしい現象も見られるようです。最近、外国産のクワガタやカブトムシがペットショップだけでなく量販店で売られていますが、堆肥や朽木採集のときなどは一瞬期待することもあります。
糞虫採集は、割り箸を持って、開けた草地をシカの糞などを探しながらウロウロします。ちょっと異様な風景ですが、さらに異様なのはシカの糞などを見つけると、しゃがみこみ、割り箸で糞を引っ掻き回して糞虫をさがします。センチコガネ類は、新鮮な糞に居り、運が良いと真新しい糞に遠くから赤い黄金色をした1センチぐらいのピカピカしたものがブーンと羽音を立てて飛んできます。
写真のゴホンダイコクは、やや古い糞の下に居り、糞の下の柔らかい部分を少し掘ると出てきます。このムシはいつもペアーで居り、糞の下に糞の玉を埋めて卵を産み付けます。
写真では良くわからないかと思いますが、小さい(約1センチ)ながら、5本の立派な角を持っています。日本最大種のダイコクコガネは2〜3センチあり、糞の下に長いトンネル(縦穴)を作り、その底に数個の糞球がはいっています。穴を掘っての採集は、スコップで回り50センチほどの穴を掘り、坑道を見つけたら、穴を見失わずに掘り進むので、根気と体力が必要です。私は、九州の平尾台で採集したことがありますが、がんがん照りの草原での作業、まだ20歳ごろのことです。東南アジアでは、夜間採集のライトに来ることがあり、大喜びしたことを思い出します。また、ゾウの糞に来るナンバンダイコクを採集したときには、現地の人たちにも手伝ってもらって掘り出したことが思い出されます。
今回は、オオセンチコガネとゴホンダイコクに、カドマルエンマコガネと呼ばれる小型のフンチュウを採集しました。早速、ティッシュペーパを細かく裂いたものを入れた茶筒に入れて、糞の汚れとお腹の中をきれいにします。

翌朝、近くの神社の建物の床下に多くのゴホンダイコクがいるということで、新しい茶筒と割り箸を持って出かけました。残念ながら、時期が遅かったのか死骸、多くはクモの巣が着いた古い死骸が落ちていました。何で、こんなところにいるのかということになりましたが、最近賽銭泥棒などの被害が多く、夜間に照明をしているそうで、周辺の山にいる獣糞を食べるフンチュウ類が飛来しているためと想像されます。寺社では夜間照明をしているだけでなく、不審者よけに人などが近づくとライトだけでなく、サイレンもなるところがあるそうです。
里山ブームのせいだけはでないとは思いますが、多くの人たちがこのような山村にまで押しかけ、動物だけでなく人まで住みにくい世の中になってきました。最近山歩きもどきをしており、山道や案内板の整備に、大変楽しい山歩きを楽しんでいますが、多くの人たちと挨拶を交わすことにすがすがしい気持ちになります。しかし、昔ながらの独り占めした自然を満喫する感動も少なくなったような気がします。年のせいかな。
八田先生へ 森島より
動物の糞をかき回している先生の姿が目に浮かびます。そばから見たら異様な光景でしょうね。でも昆虫はどこにでもいるので、ムシヤさんは楽しくてしょうがない?
虫捕り記?5(2011.6.11)
森島さん、山歩きの助言ありがとうございます。
自分の足にぴったり合う登山靴
急に週2回ほどの2万歩を越す山歩きが続いたため、靴が大きかったせいか左足に大きなたこが出来ました。近場では、やや靴が大きいかなと思うぐらいでしたが、早速、足にあった靴を買ってきました。
今回は、前回に紹介した森島さん御推薦の石津山から多度山への縦走コースに挑戦。
インターネットで、石津山の情報を手に入れたら、山歩きの人のブログに写真入で紹介があったので、印刷して出かけました。ただし、ハイキング情報なので、お寺など散策地が中心でした。やや不満足な感があり、今度は近鉄のハイキングコースなどを見ることにしました。ネットで探すと、結構面白いことに改めて気づきましたが、はまり過ぎないようにします。
そこで、今回の失敗談などを少し書きます。いつものとおり、多度までは自転車(ママチャリ)でやく1時間。木曾三川を越えるのですが、川の上を自転車で走るのは行きか帰りには大変な向かい風。ボツボツママチャリを卒業せねばと、いつも川越の急坂越えと橋で反省。
そこから養老線で石津駅へ。養老線は近距離にもかかわらず運賃が非常に高いのですが、自転車ごと乗れるのは最高。それに加え、電車賃は自転車の分は無料。ただし、特別な仕掛けはなく、手で倒れないようしっかり待たなければならなく、結構ゆれるので大変。慣れた人の乗車を見ると、前か後ろの席に座り、前の車輪を電車の角で止まるようにしてスタンドを立てていました。早速、私もまねをしましたところ、楽チン。無人駅と桑名駅では、乗降は出来ないので、要注意。時間帯も10時ごろから3時台の乗降客の空いている時間帯のみです。
もう一つ、ありがたいことに、有人の駅ではマウンテンバイクのレンタルが、1日100円で借りられることです。ただし、各駅に数台しかなく、予約が出来ないので、平日の駅に自転車が止まっているときだけなので行き当たりばったりです。
さて、石津駅降車、この日は歩きで行くのですが、石津駅を降りたのは私一人。駅前には、店も人もいなく、仕方がないので、前に見える車が通る道まで出て、雑貨屋兼洋装店の前で話をしているおばさん二人に道を尋ねる。ついでに、コンビニかパン屋さんでもないかと聞くが、このあたりには店はまったくないとのこと。うっかり、電車を降りて弁当でも買えばとの安易な気も砕かれる。それでも、国道を越えて登山道に出るので、どこか探せばあるだろうと安易に考えていたが、墓掃除をしている若い婦人に聞くと、国道をまっすぐ行けばあるとのこと。20分ほど歩いてもないので、畑をしているおばさんに聞くとまだまだ先とのこと。あきらめて自販機でお茶だけを買い、登山口まで歩く。山歩きの準備の基本をここでしっかり思い知る。お恥ずかしい。そこで、12時まで登り、下ることにした。
石津御嶽山へは、ふもとの神社から急なのぼりが林の中を続き、4合目当たりに見晴台があり、そこからしばらく稜線を歩き、また最後の登りと続きます。登山道に関しては、多くの登山者のブログで見てください。3日後には養老線の二駅北にある駒の駅から月見の森に出かけました。
このコースは 「近鉄発行のハイキングコースマップ」を見て、http://himajinclub.boo.jp/kintetu/kinntetu.html地図は近鉄の「散策・ハイキングマップK's PLAZA」http://www.kintetsu.co.jp/event-hiking/sansaku/tekumap.htmをコピーして出かけました。駅近くの道路は詳しいが、登山道の地図は少々わかりにくい。
今回の採集品の中で、今回は動物の糞を食べる糞虫と呼ばれる仲間のなかでも非常に美しいオオセンチコガネの写真を添付します。写真ではわかりにくいのですが、左は赤銅色、真ん中は緑色の個体で、きれいに輝いていますが、右の個体は少し小型で黒いセンチコガネです。オオセンチコガネには、奈良のシカの糞を食べるルリセンチコガネと呼ばれる瑠璃色に輝くオオセンチコガネが有名です。最近この地域(多度山系)にもシカやサルが増えているせいか、この日は5匹ほどゲット。

来週の金・土曜日には、高校の生物部の先輩に誘われて神戸の奥に採集に出かけます。高校の生物クラブの仲間4人なので、夜のお酒がこわい。
森島さん、野島さん御夫妻
ニュージランドへの出発に、わくわくしていることと思います。JAMUSたち家族と酒林さんの息子、娘さんともお会いできるのでしょうか。皆様に よろしくお伝えください。お土産話を楽しみにしています。お酒の飲みすぎにくれぐれもご注意。ニュージランドの昆虫、および採集事情がわかれば聞 いてください。では、お気をつけて出発ください。
八田先生へ 森島より
石津駅からの登山情報を伝えなかったことを反省しています。同駅近辺にはコンビニも食料品店もありません。民家と医院があった程度と記憶しています。細い道を迷いながら歩いて、みかん畑の中から登山道が始まったようなことを覚えています。
前回、登山に必要な3つの装備を書きましたが、食料や水については当然だと思い書きませんでした。でも苦労の末、オオセンチコガネを5匹もゲットできてよかったですね。
ニュージーランド行きについては、大震災後でNZ航空のスケジュールが大きく変わった り、わたし個人の仕事の関係でキャンセルせざるを得なくなりました。期待されていた野島さんには申し訳なく思っています。落ち着いた時点で再度計画を立て
たいと思っています。Jamesはわれわれの訪問に備えて庭のリフォームもしたようで、かれらにも申し訳なく思っています。毎日のように彼からはメールが 来ており、早くみなさんとNZに来てくださいという内容です。
海田 雄治
郊外緑地の池にカイツブリの家族がいます。1か月ほど前に孵化した一羽の1番子は母親が抱卵中 の巣に近づきたいようですが、父親が猛烈な勢いで追い払います。1週間ほど前に孵化した矢張り 1羽の2番子は母親に甘え放題、父親から餌を貰っています。2番子の可愛い様子と、独り立ちさせ られた?1番子の可哀そうな姿が見られました。3回目の卵4個を抱卵中です。
八田です。
すばらしいカイツブリの親子の写真、いつ見てもほほえましいですね。
ご存知のように野生の動物で見られる子離れの儀式ですが、雛の悲しそうな声としぐさはなんともいえない野生の厳しさが感じられます。これらの一連の行動は、縄張りと近親相姦を避けるために出来るだけ遠くに子供を遠ざけるための親、特に父親の行動と知られています。ただ、それだけでなくオス のメスとの交尾行動、オスの遺伝子を残すためともとらえられていますが、改めて野生動物の厳しさと人間的な解釈でありますが理にかなった行動のようですね。熊のような肉食獣には、子供を殺すこともあるようです。ただ、2番子を追い出さずに抱卵していることは知りませんでした。このようなことは、小鳥では良くあることなのでしょうか。
そこで、昆虫界の面白い話を紹介。海上の森でも多く見られるカワトンボの仲間は、オスがメスのお腹の中にある貯精嚢(精子をためておくための袋)の中の前に交尾したオスの精子を掻き出して、交尾をすることが知られています。
モンシロチョウでは、交尾後のメスはお尻を上げて翅をやや下にして交尾拒否の行動が見られます。一度モンシロチョウが多く見られる吸蜜しているところを観察してみては。オス、メスの違いは慣れてくると一目でわかりますが、メスのほうがやや大きく、少し黒っぽく見られます。
また、ギフチョウやウスバシロチョウで見られる交尾後に見られる尾端の交尾嚢はよく知られています。哺乳動物ではウサギが知られています。
八田先生 みなさん こんばんは。海田 雄治
昆虫や野鳥の巣立ちのころの様子について解説いただき有難うございます。このカイツブリについては2カ月ほどの間に5回ほど見に行きましたが、1 回目は4個の卵が産まれましたが、僕は見ていませんが 蛇、雷魚の餌食になり1羽だけ孵化したそうです。その子育て中に2番子の交尾、産卵が行われ2番個 も卵は4個でしたが、また蛇の餌食になり卵が1個になり、色が茶色っぽくなり 間もなく孵化と思っていたときに 真っ白の3回目の卵がまた4個生まれまし た。従ってこの子達は1羽雛がいたところへ次の産卵ではなく、前の卵が1個有った所へ新たに産卵が有ったということです。(聞いた話も含みます)
他の小鳥でカワセミ、サンコウチョウで雛が巣立つ前に交尾をしているのは何度か見たことが有り
ますが、いずれも巣の中は見えませんので様子から推測で、産卵は巣立った後のようでした。
八田先生へ 森島より
近親相姦は人間同士に付いてのことばで、動物では近親交配ではないでしょうか?
間違っていたらゴメンナサイ。
八田です。 海田さん、森島さん、皆様
近親相姦は生々しすぎですね。生々しい話をもう一つ。鳥や蝶などのオスがきれいなのは、メスを 誘うためとか、きれいなほうがメスに好かれるとよく 言われますが、相手を選ぶ決定権がメスに あるのでなく、人間も含め動物はオスによる略奪婚だと考えています。同様に小鳥やセミ、鈴虫の 鳴き声はきれいな声でメスを誘うようですが、メスから誘うこともあるのでしょうか。
カイツブリの繁殖行動は3回とも同じ父親でしょうか。オシドリ夫婦のたとえのオシドリは、必ず しも同じ夫婦が続いているとは限らないと最近新聞で見たような気がします。カイツブリも不倫が あるのでしょうか。
どなたか、教えてください。浮気に縁のない八田旦那より。
海田 雄治
他の小鳥でカワセミ、サンコウチョウで雛が巣立つ前に交尾をしているのは何度か見たことが有り ますが、いずれも巣の中は見えませんので様子から推測で、産卵は巣立った後のようでした。 昆虫少年?虫捕り記4(2011.6.5)
今年4回目の多度山行きです。5月30日9時に自宅を自転車で出発。途中、木曽三川公園を見ながら多度大社に1時間かけて到着。
多度大社脇の駐車場(土日は有料)の隅に自転車を置く。出発準備をしていると、桜の葉にヘリグロベニカミキリ(2cmほどの大型で、きれいな赤色:左))を発見。幹にはヨコヅナサシガメが。あわてて手で採ると手指に激痛が。

最近、名古屋でも温暖化の影響か、桜の木に大発生。冬は桜の幹のくぼみで越冬、春に成虫になる。名前の通り刺すので注意が必要。刺されないようにつかんだのですが、洗礼に遭いました。刺されないよう注意がするのですが、どれだけ痛いか知らなかったので、良い経験になりました。スズメバチの痛さも1昨年経験しましたが、それほどでもないのですが2度と経験はしたくないほどの痛さでした。
その後は、前回紹介した多度峡をたたき網で小さな甲虫類(ハムシやコメツキムシ)を落としながら、山頂へ。途中で、カワトンボやカワゲラ、ムシヒキアブなどをゲット。小さいのがほとんどだが、約200匹(頭)ほどを採集。頂上付近ではきれいなオオセンチコガネやヒメオサムシを拾うなど、満足の採集行でした。
海の見える展望所で13時ごろおにぎりを食べ、今回は前々回(13日25000歩)下りで使った健脚コースでなく、眺望満喫コースを通り、途中のポケットパーク駐車場からのんびりコースで下山。最後に、モリアオガエルの産卵塊を2箇所で見ることが出来ました。
今回、寄らなかったのですが、多度峡天然プールを過ぎてすぐに急なわき道を10分ほど登ったところにイヌナシの自生地とみどりヶ池があります。なかなか良い池ですので、一度行くことを進めます。
全行程3万歩、5時に多度大社に到着。多度名産のアイス饅頭を食べながら自転車で帰宅の徒へ。
次回は、森島さんのお勧めの石津御岳からお届けします。
八田先生へ 森島より
楽しそうな虫捕り記を読みました。
山に入るときの必需品3点は以下のとおりです。
1) 自分の足にぴったり合う登山靴
2) 蒸れない雨具
3) 汗をかいても冷えない下着
あとは好きな食料を持参すれば安全で楽しい山歩きができます。
石津御岳から多度山への縦走も楽しいものです。石津駅から登り、多度駅へ降りて、養老線で石津駅まで戻るのですが、車窓から今歩いた稜線を見るのもいいものです。
いつまでも登山兼虫捕りを続けてください。
昆虫少年?虫捕り記3(2011.5.21)
5月は、海上の森に3回も行きました。
19日には、海上の森のトンボ池を見てきました。万博には会場から外れていたのですが、柵が張り巡らされていて大きく変わっていました。ただ、万博関連の道路が出来たため、湧水が涸れたためにボーリングをして真っ赤な(土壌中の鉄バクテリア)湧水が噴出していたところには湿地が拡がり、ハッチョウトンボが昨年は多く発生したようです。ハッチョウトンボは休耕田のように放棄されたたり、改変された(撹乱)ときには一時的に大発生するようです。愛工大の先生が昨年から調査をしておられます。
しかし、その周辺は驚くほど、万博前の面影がありません。万博協会の環境部長とやり取りした湿地や禿山、ブッシュがきれいに整地された状態でし た。見える限りは松などを植えているようですが、登り窯の採掘をしていた場所がどうなっているか気がかりです。こちらのほうがハッチョウトンボが多かったように記憶しているのですが、県が保全していると思うのですが、最近の状況をどなたか知りませんか。一度見に行きたいと思いますが、どこが管理しているのかわかりませんか。
森島さんと上田さんに乗せられ、少しムシの話を書きます。
写真は小さいので、図鑑で確認してください。海上の森でも普通に見られる虫で、面白そうな虫を紹介します。
写真は、上左から
ヒゲコメツキ:体長は2cmぐらいで、裏返すとペチンとはねるので目立ちます。コメツキムシ科は日本で600種以上が記録されており、小さくて黒か褐色のほとんど素人では区別できない種が多い中でもひげが長いので特徴的です。
アカハネムシ:1cm強あり、赤くホタルのようなので目立ちますが、ベニボタルとよく間違えられます。両科ともに20種、90種以上がいます。
ヒメオビオオキノコ:キノコにつく虫の仲間で、1cm以上あり、黒に赤色の帯があるため非常に目立ちます。約100種ほど知られています。
下左から
キクビアオハムシ:ハムシ科は500種以上が記録されているが、前回紹介したサルハムシの仲間の様にきれいな仲間もいるのですが、非常に似たものが多く、コメツキ科の様に同定(種名の決定)が難しい。その中でもこのムシはきれいな緑色に輝いているので目立つが、ウリハムシ属やいくつかの種と間違うことが多いので気をつけなければならない。特に絵合わせをするのでなく、特徴を正確に。
セモンジンガサハムシ:ハムシの仲間でも形に特徴があり(昔の足軽の陣笠に似ている)、比較的同定が簡単そうだが、微妙に違うので要注意。
ツバキシギゾウムシ:ゾウムシの仲間は、ゾウムシ科(約650種)、ヒゲナガゾウムシ科(200種弱)、オトシブミ科(100種弱)など5科で構成され、細かくいくつかの亜科に分かれており、あわせてゾウムシ上科としている。
名前の通り長い鼻(吻)をもっているので象の鼻をもじって呼んでいるが、昆虫には人間のような外鼻はなく吻の先に触角を持っている。その中でも吻が体長とほば同じ長さ(メスは体長より長い)を持っており、非常に特徴的であるが小さいため、見逃しがちであるが、これから椿を見るときは一度探してみては如何。
じっくり見ると面白いのが見つかると思います。いいのが見つかったら、八田まで。

八田先生へ 森島より
そういえばトンボ池という名の池があり、先生と何度も見に行ったことを思い出しました。10年ぐらい前でしょうか。そのときは、道路ができると水脈が切断されて池が乾燥してしまうと反対運動をしましたね。やはり涸れてしまったため、ボーリングをして人工的に湧水をつくっているのですか。あの地域一帯は県が買収したため、管理をしているのは県ではないでしょうか。海上の森センターに聞けば分かると思います。
ムシの写真を見て、どれもよく見るものだなと思うのですが、実際はそれぞれ何百種類も似たものがいるのですね。鳥とは違って、まだ見たことが無い種が膨大な数あるのですから、いつまでも自分にとっては新発見が続くわけですね。
八田先生、上田♂です。
虫講座ありがとうございます。ちょっと早いですが、今日は芋焼酎にして図鑑をひっくり返しなが ら楽しんでいます。ムシクソハムシなんて虫界のヘクソカズラみたいなかわいそうな名前を見つけ て喜んでいます。
添付の写りの悪い写真は、何年か前の7月の終わり頃撮ったのですが、動いていたので虫だと思う
のですが何でしょう。

八田先生へ 森島より
上田♂さんに便乗して質問します。
写真の蛾は昨年の5月に能郷白山で見たものです。
名前が分かりません。教えてください。

八田です。
上田さん、イボタガで正解です。私の標本箱の中にも長久手で採ったのが1匹翅を広げて展翅した状態で入っています。名前を調べるときには、種の特徴の細かいところもわかるように、そして隠れたところも出来るだけ見えるように展翅してから調べます。以前紹介したインタネット図鑑には、生態写 真が載っています。岐阜大学の理科教材データベース、昆虫図鑑には、上田さんのご質問のベッコウハゴロモの幼虫として載っています。この仲間の幼虫は羽毛をかぶったようなものが多く、我が家の庭にはアオバハゴロモの幼虫がここ3年ほど前から大発生しています。近いグループに、木の枝にくっついた蝋や綿のような移動が出来ない、カイガラムシという昆虫とは思えないような虫もいます。
もう1杯飲みながら見てください。
昆虫少年?虫捕り記2(2011.5.15)
やっと春らしくなり、昆虫少年も虫捕りに興じています。森島さんほどの健脚コースでなく、近場を歩いています。
13日には、多度山まで登り、24,000歩歩いて、その夜は足がつるほどでした。多度神社に車を置き、多度峡を登り始めたのが12時。
ビーティング(たたき網に虫を落とす)をする度に虫が落ち、2kmを歩くのに2時間以上かかるなど久しぶりに虫捕りに興じました。川筋にカワトンボやサナエトンボが舞い、風が強い為蝶は残念ながらほとんど見られなかったが、カワゲラやカゲロウの羽化時期のため採るのに意外と時間を費やしたため次回の楽しみに先を急ぎました。その後、山道を歩き山頂近くで、白い花に集まっているカミキリなど、これから夏が期待できるコースでした。
森島さんも勧めていたとおり、なかなかいろいろなコースが楽しめそうで、これから多度参りが続きそうです。明日は守山の細流と海上の森、夜に名東区の塚のいり池で夜間採集と欲張ったコースを歩きます。あさっては、清洲市の小学校のがさがさ隊(水生動物観察)で庄内川に行きます。その後は特別予定がありませんが、多度山を中心に歩こうと思います。また、良い企画があったらお誘いください。
添付の画像は、13日の採集成果です。

約200匹ぐらいですが、ゴミみたいな中にきれいなサルハムシなどもおり、捕まえたときのにやけ顔をご想像ください。

サルハムシの仲間はきれいなハムシですが、その中でもアカガネサルハムシはすばらしい光沢があり宝石のようです。大きさもちょうど指輪サイズです。
写真を入れておきましたが、図鑑で確認ください。
八田先生へ 森島より
タイトルを「虫捕り記」にして毎回報告していただくとみなさんが楽しんで読んでくださると思います。先生のにやけた顔を思い浮かべながら。
サルハムシは猿葉虫と書くのですね。どこにでもいそうですが珍しいのでしょうね。
昆虫少年?虫捕り記1(2011.5.12)
上田さん、森島さん
難しい注文、ありがとうございます。小さい画像送ります。もともと小さい虫ばかりなので(ミリ単位)、大きくしても面白くないと思います。ただ、何もいないのに、30種ほどいました。
一番大きそうなので、1列目のトップバッターのシモフリコメツキの13mmです。その隣がアカコメツキ、クロスジヒメコメツキ、ホタルハムシが3匹、最後の小さなのはわかりません。
2列目はカバノキハムシ、キセスジハムシ、その隣の2種はハムシですが、わかりません。その隣の少し大きいのは(3mm)ルリマルノミハムシ、隣の小さいのはトビハムシの1種です。ハムシの仲間は、日本では500種ほどおります。
3列目は、ヒゲボソゾウムシの1種、クチブトゾウムシの1種、クチブトゾウムシの別種、クロボシツツハムシ、ホソハネカクシの1種が3匹、コガシラハネカクシの1種。
4列目は、キラチャイロコガネ、マルガムシが3匹、ナミテントウ二紋型、ヤマトヒメカゲロウ、シマトビケラの1種5列目は、ホソアワフキ(草に人の唾がついているのかと思われる泡の中に幼虫がいます)、クルミヒロズヨコバイ、クロカワゲラの1種が3匹、クロカワゲラの別種が2匹。
6列目は、ハナバチの1種が3匹、ホソハバチの1種、オドリバエの1種、オドリバエの別種が7列目までの9匹(これは我々の目の前をうろちょろ 飛んでいたブユと言っていたものです)

ごちゃごちゃと書いてきましたが、楽しかったでしょうか。余計酒の量が増えそうですね。日本でこんな小さい虫を相手にしているより、早く台湾で虫捕りがしたい。ストレスがたまりそう。
八田先生こんばんは上田♂です。
4日の段戸裏谷で採集された虫の整理はお済みでしょうか。MLでは初になると思いますが、採集された虫の報告をお願いできませんか。確かハネカクシの仲間だったと思いますが、気になって焼酎の量が増え気味です。お願いします。
八田先生へ 森島より
平地より低温度の段戸では昆虫はあまり期待できないと思っていましたが、採集できたようですね。ぜひ報告してください。それによって他の人も昆虫に関心が増えると思います。気にならなくても酒量が増える上田さんからの依頼ですし。
八田先生へ 森島より
既に「虫捕り記」が始まったようですね。その調子でいろいろ毎日記事を送ってください。投稿者が固定してしまっていますから、いろいろな人が発信して下さるのは大歓迎です。よろしくお願いします。