名古屋市環境科学研究所の見直しへの市民検討会提言 20101217
名古屋市環境科学研究所のあり方を考える市民検討会
座長 鈴木 茂 (中部大学)
前文
私たちは名古屋市が進めている環境科学研究所の「ゼロベースからの見直し」には,大いなる不安を感じている。この「見直し」が,財源難を理由に一部の自治体で行われている環境研究機関などの縮小,廃止を目的とするものなら,行政機関の小組織である環境機関の縮小は不合理であり,「見直し」は大いなる環境軽視である。
20世紀後半,国と県と市が環境研究に裏付けられた施策によって「目に見える公害」の多くを解決したことは,大きな成果であった。しかし,激化する気候変動,天文学的な種類の化学物質,増加する廃棄物,枯渇する資源など,人類が生き続けるための環境は悪化の一途を辿っている。その根本的な原因は「大量消費を経済の原動力とする社会」にあり,時間をかけてそのような経済の仕組みを改めない限り環境悪化の流れを止められない。名古屋市は「名古屋市の環境に責任を負う」とともに,地球のコミュニティのひとつとして地球全体の環境にも配慮した環境施策とそれを裏付ける環境監視,環境調査,環境研究を進める義務がある。そして将来的には市民生活を支える経済を過剰な生産から文化,福祉,環境などの産業に転換し,環境に負荷の少ない経済社会を作るために努力しなければならない。名古屋市環境科学研究所は,名古屋市の環境を調査,評価し,環境施策の科学的基盤を担う組織であり,名古屋市は環境科学研究所を最大限に活用する「見直し」を行い,強化することこそ、環境首都名古屋にふさわしい。
私たちは,名古屋市環境科学研究所の「見直し」について耳にする民間分析機関,大学などへの事業委託が,環境軽視の施策にならないか懸念を持つ。環境事業の効率化に委託が有効な場合はあるが,委託する組織の現状を詳しく把握するべきと考える。これまで環境調査に関する経費は官,民を問わず極めて低い水準に抑えられ,一般に分析価格は低く,多くの民間分析機関では分析内容の検討,評価などを行う時間的,経済的余裕が乏しい。また大学等の外部研究機関は,特定の専門分野の研究には優れているが,地域の環境を総合的,恒常的に研究することはできない。名古屋市は,環境関連事業の委託によって名古屋市の環境監視,環境技術,環境評価などの能力低下を生じないことを常に検証し,それを公開する必要がある。環境関連事業の委託は,名古屋市の環境施策の効率化を目的とするが,研究分野の委託に際して環境科学研究所を参加させるなど,名古屋市の環境研究の力量を高めるべきである。
私たちは名古屋市が「名古屋市の環境は名古屋市が責任を負うこと」を基本に,現時点で求められる環境科学研究所の在り方をここに提言する。この提言を広く市民に公開し,内容を深め,名古屋市と名古屋市民が協力して,名古屋市と地球の環境改善に取り組めることを心から期待する。
提言
提言の基本
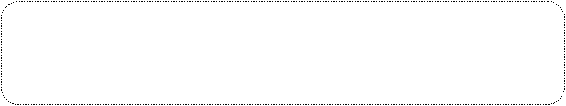 ①名古屋市の環境に責任を持ち、公害対策、環境保全に寄与する研究所となること。
①名古屋市の環境に責任を持ち、公害対策、環境保全に寄与する研究所となること。
②名古屋市環境科学研究所が、市民に開かれ、市民の要求に応える研究所となること。
研究所に求める機能
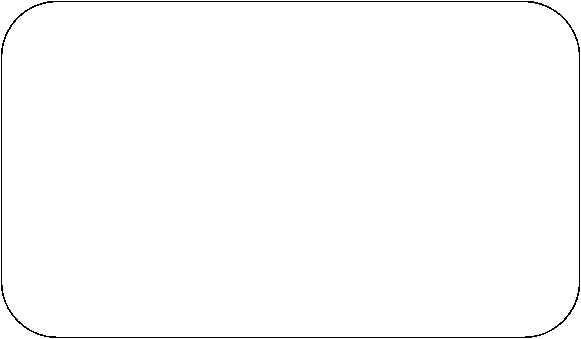
提言内容
市民のための名古屋市環境科学研究所にするために、研究所は以下の機能を有すること。
①発生源と環境を監視する機能。[監視機能]
②事故、災害時における汚染物質の漏洩・拡散や未知の汚染物質による健康被害の恐れに対応する機能[危機対応機能]
③様々な調査を通してデータを取得し、それを解析する機能。[調査解析機能]
④現状の環境問題及び新たな環境問題に対応するための調査研究機能。[調査研究機能]
⑤市民の活動を科学技術的に支援する機能。[市民サポート機能]
⑥環境行政を科学技術的に支援する機能。[行政サポート機能]
⑦蓄積されたデータや情報を解析、整理、発信する機能。[情報発信機能]
◆提言説明
見直しと提言の基本を実現するために、研究所に必要な機能を7つあげた。
これら7つの機能は、相互に関連しているため、単純化して単独に論じるべきではないが、便宜上、それぞれについて提言内容の補足説明を以下に示す。
①[監視機能]について
「『地域住民の安心・安全を科学的側面から保障する機関』であることが、地方環境研究機関の重要な役割の一つであると思われる。」と、「地方における環境調査研究機能強化に向けた提言(環境省)」にも示されている。モニタリング機能は、そういった役割を実現するための根幹的な機能と言える。また、日頃から定常状態の環境を長期間にわたり、モニタリングしていることで、分析技術の向上、知識の蓄積がなされ、突発的な環境汚染などの緊急事態への迅速な対応力が培われることにもなる。
(注)安易なアウトソーシングは、必ずしも経費削減には繋がらない。
目先の費用対効果だけではなく、アウトソーシングにより失われる部分(分析能力や技術的なノウハウ、汚染実態などの評価能力などの人的な資源)、アウトソーシングにより新たに発生する部分(精度管理に伴うデータの信頼性確保に関する業務など)も含めて、費用対効果を考慮すべきである。
②[危機対応機能]について
事故、災害時に事業所等から漏洩、拡散した汚染物質による周辺地域への影響を把握したり、原因不明な汚染物質の存在が疑われる際に、原因物質の特定、汚染範囲の確認を行ったりするものである。
汚染状況や汚染原因物質を迅速に把握することで、市民への注意喚起を呼びかけるなどの行政対応をサポートし、市民の健康と安全を確保することができる。
そして、より迅速な危機対応をするためには、汚染物質を分析する機器を整備することや体制づくりが必要である。
③[調査解析機能]について
フィールド(現場)を持ち、長期的かつ継続的に行う調査や環境の現況を把握するために行う調査でデータを取得し、それらについて解析を行うものである。
例えば、法律で規制されていない有害な化学物質による環境汚染などにより、市民の健康が害されることがないようにするためには、現在の汚染状況の把握が必要となるが、実態調査を行い、その結果を評価することにより、環境汚染の有無や対策の必要性がわかる。
④[調査研究機能]について
現在直面している環境問題の解明や対策に結びつく短期的視野に立った調査研究及び将来発生するかもしれない環境問題へ対応するための中長期的視野に立った調査研究の両方が必要である。
研究テーマについては、上記モニタリングや調査解析において、顕在化してきた環境問題への対策の延長上にあることも少なくないが、行政のニーズや市民のニーズを反映させるしくみづくりが必要である。
⑤[市民サポート機能]について
長期間、継続的にデータ、技術、知識を蓄積している研究所は、環境に関わる市民活動を技術的に支援するべきであり、市民の求めに応じて、適切な情報提供や技術的支援をする機能は、研究所に必要不可欠である。
また、「市民参加のNO2測定」、「環境調査結果の読み方教室」、「簡単な分析作業研修」など市民が環境活動をしていくために必要な技術や知識を習得できるようなものを実施することにより、一方的な支援ではなくて、市民協働型の取り組みを行っていくことも必要である。
⑥[行政サポート機能]について
様々な行政部門と研究所の連携を強め、専門職を政策立案に活用されるしくみを作ることにより、長期間、継続的に環境調査や研究を行ってきた研究所が、科学的な立場から適切に行政をサポートすることが必要である。また、行政が市民への説明責任を果たす際に、客観的な判断材料を提供することが期待される。
なお、上記行政サポート機能を実現するためには、研究所職員の専門性を担保する必要があり、必要に応じて研修制度の導入を検討すべきである。
⑦[情報発信機能]について
研究所には、長期間、蓄積された調査データや技術があるが、それらをわかりやすい形にして、行政や市民に提供することは、研究所の義務である。
地域に根ざした名古屋市の環境について、科学技術的に情報提供することは、研究所が担うべき機能の一つである。
市民参加の仕組み
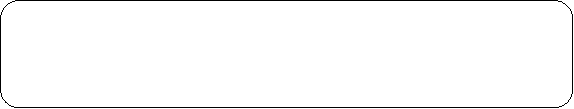 提言内容
提言内容
(1) 市民に開かれ、市民から見える研究所とするために市民参加、情報開示と情報
発信を強める。
(2) 市民の期待に応え、市民の目線で評価される仕組みを作る。
①研究と業務内容は可能な限り公開する。ホームページ等には、過去の研究、業務の成果とともに現在進行中の研究、業務の概要を掲載する。
②年間の研究、業務の成果を市民に報告する会を開催する。また市民懇談会など市民の声を聞く場を設ける。
③研究所は、年ごととある程度長期の研究業務計画を策定する。策定にあたっては後述の「運営協議会」と市民の意見を聞く。
④年度内の研究所の研究、業務の内容を精査し、公害対策、環境保全に寄与するものであったか、市民に開かれ、市民の要求に応えるものであったかの視点で評価する「運営協議会」を設置する。「運営協議会」は評価と次年度への提言を行う。「運営協議会」の評価と提言を市長、管轄部局と研究所は最大限尊重して、必要な改善、取り組みを行う。
⑤「運営協議会」の協議と協議結果は原則公開とする。
⑥「運営協議会」の市民委員は公募で選出する。
以上
名古屋市環境科学研究所のあり方を考える市民検討会
○座長:鈴木 茂(中部大学教授)
○メンバー:鈴木茂(中部大学教授)、村上哲生(名古屋女子大学教授)、八田耕吉(元名古屋女子大学教授)、土井敏彦(医師・愛知県保険医協会公害環境対策部長)、松田勝三(名古屋かわを考える会代表)、土山ふみ(名古屋学院大学非常勤講師)、小島節子(元環科研主任研究員)、長谷川恒夫(旧公害研究所(現環科研)研究員)、他
○事務局:愛知県保険医協会事務局・村上
〒466-8655 名古屋市昭和区妙見町19-2
TEL 052-832-1346 FAX
052-834-3584 Email:s-murakami@doc-net.or.jp
資料 名古屋市環境科学研究所の在り方を考える市民検討会について
20101216
1.これまでの主な経過
2009年11月16日 名古屋市が研究所「廃止」表明
11月、12月に労組支部から廃止撤回要求
12月 全国の研究組織から存続を求める要請
12月17日 県下環境団体が共同で廃止撤回、存続を求める申し入れ
その後、各団体が名古屋市に申し入れ、懇談など
2010年
2月市議会で市長が「廃止は言い過ぎ、ゼロベースの見直し」と修正
4月10日 名古屋市の環境行政の後退を考える学習シンポ(いっせい行動主催)
4月 環境省が「環境調査研究機能強化に向けた提言」発表
5月7日 「いっせい行動」実行委員会が要請書提出→6月18日に回答着
5月14日 名古屋市議会が「存続を求める請願」を全会一致で採択
7月27日 愛知県保険医協会が「見直し検討会」へ3点の要望書提出
8月31日「いっせい行動」の話合いで市長が「見直し検討会」として市民の意見も聞く
場を持つと表明
2010年7月29日 市の検討会・作業部会が第一回合同部会
9月29日市の検討会に市民検討会が要望書を提出
2.市民検討会
8月3日 市民検討会準備会、検討会発足 13人出席
以後、市民検討会を8月27日、9月7日、9月22日、10月6日、10月19日、11月8日、11月22日、12月13日の8回開催。
10月30日にシンポジウム「 名古屋市環境科学研究所のあり方を考える」を開催。
1)会の目的
市が「ゼロベースでの見直し」を開始した名古屋市環境科学研究所について市民の目線から組織、業務などの見直しを行い、今後の在り方を名古屋市に提言する。
見直しと提言の基本は、
①名古屋市の環境に責任を持ち、公害対策、環境保全に寄与する研究所となること。
②名古屋市環境科学研究所が、市民に開かれ、市民の要求に応える研究所となること。
2)会の名称
名古屋市環境科学研究所の在り方を考える市民検討会(略称:環科研在り方市民検討会)
3)会の構成
○座長:鈴木 茂(中部大学教授)