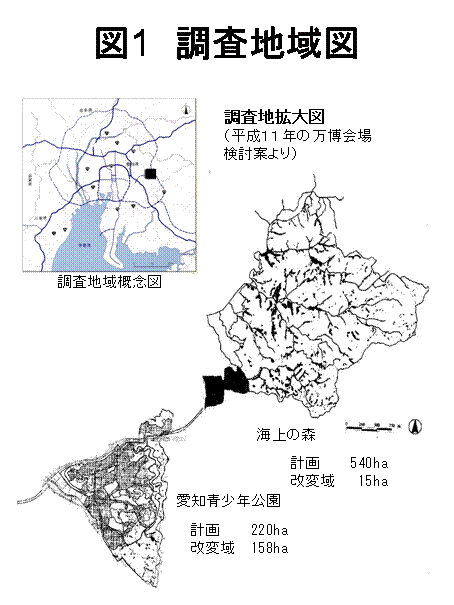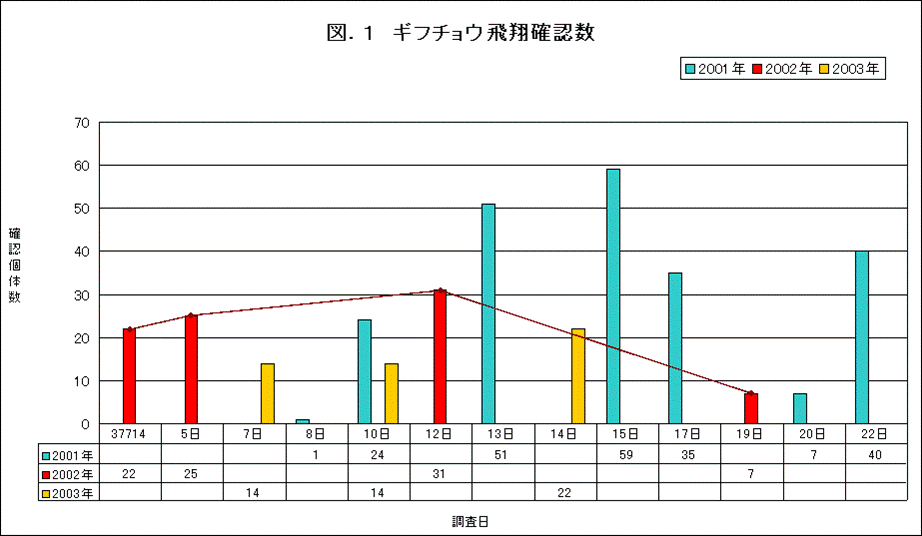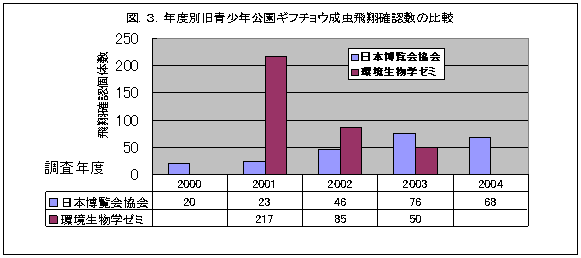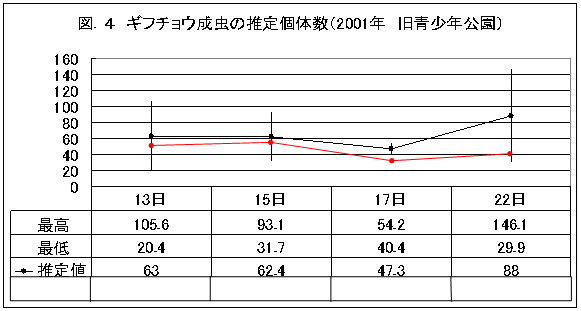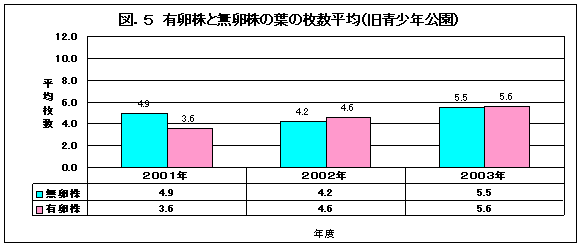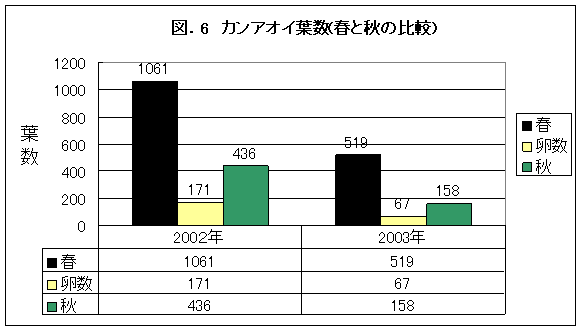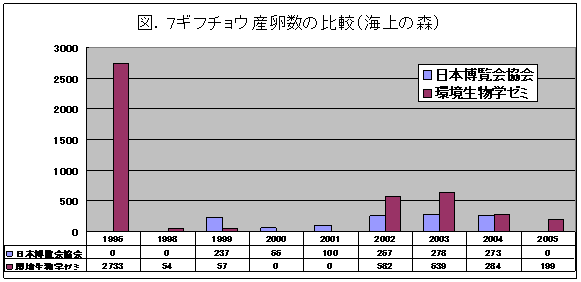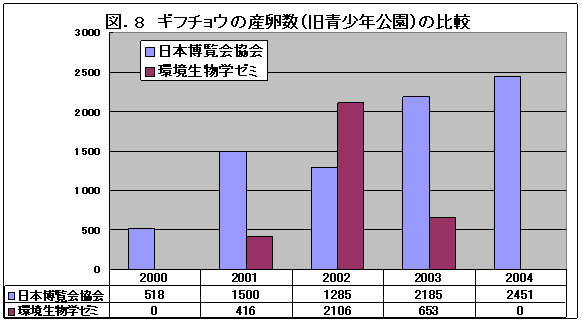里山の指標となるギフチョウの保護
八田 耕吉1)・広木 詔三2)
1) 467-8610
2) 464-0814
The preservation
of Luehdorfia japonica which becomes the index of
Satoyama ecosystem
Kokichi Hatta1)
and Syouzou Hiroki2)
1) Environmental Biology, Nagoya Women’s Unuversity,
3-40 Shioji-cho, Mizuho-ku,
2) Forest Ecology, Nagoya Unuversity, 1 Hurou-cho, Chikusa-ku,
Abstract:As a preservation action of the Satoyama
ecosystem (Mt village ecosystem), Luehdorfia japonica
(Leech) inhabiting Kaisho-no-Mori Forest and Aichi
Youth Park has been monitored from the years of 2001 to 2004.
Key words Lepidoptera, Satoyama ecosystem, population, Luehdorfia japonica,
Asarum kooyanum .
はじめに
現在, 日本における貴重な財産として注目を浴びている里山生態系の保護について, 東海地方においても環境アセスメントが実施されている. 愛知万博では, 会場が瀬戸市の海上の森から長久手町の愛知青少年公園に移され, 2002年7月に環境アセスメントの修正評価書の確定が行われたが, 里山の重要性を評価するシステムが現状では確立されているとは言い難い (八田, 1998, 2000).
新しいアセスメントの精神に沿った調査を行うためにも, 貴重種の保全のみにとらわれた調査ではなく, バックボーンとなる周辺地域と一体となった生態的な視点に立った調査が必要となる. 愛知青少年公園は都市公園として長く整備されてきたため, 自然度が低いように一般的に評価されているが, 30年程前にこの公園がつくられた時 (1970年開園) から手をつけられずに残されている雑木林が南部に大きく残され, ギフチョウ (Luehdorfia
japonica) の棲息地 としての地域一体は, 海上の森をはるかに上回るギフチョウの楽園である.
長久手町・愛知青少年公園において, 2001年から2003年にその基礎資料となるギフチョウの個体群動態についての調査を行った. また, 瀬戸市・海上の森における1998年, 1999年の調査結果と, 2002年から2004年に行った調査も併せて検討を行った. 併せて博覧会協会が行なった2000年から2004年までの調査結果とも比較検討した. 里山型の生物との共存のあり方を探ることにより, 個体群の維持できる大きさ, 保全すべき地域全体の面積や方法, 保全のための回避・低減・代償措置のあり方について検討するための資料とした.
調査方法
ギフチョウの個体数推定の基礎資料を得るために, ギフチョウ幼虫の食草であるスズカカンアオイの分布とギフチョウの産卵との関係を把握することを目的として, 下記に挙げる調査を行った. 本報告では2, 3項を中心に述べる.
1. スズカカンアオイの分布及び分布密度 (広木ほか, 1999a, b)
2. ギフチョウ成虫のマーキング調査
3. 卵及び若齢幼虫の調査
調査は2001年より行い, 調査地域は愛知青少年公園 (2001年から2003年) と海上の森 (2002年から2004年) とした(図1). なお, 愛知青少年公園 (全体で220 ha) は, その約7割に当たる158 haが2005年愛知万博の長久手会場とされて2003年より造成工事が始まり, 現在は万博跡地のまま休園されている. このため, 以下本文では旧青少年公園と呼ぶことにする.
調査期間は, 成虫は4月の上旬から, 卵と幼虫は4月下旬から5月中旬まで行った. 成虫調査は, 羽化して山頂部で飛翔する (ヒルトップ) ギフチョウを捕獲又は目視し, 捕獲した場合は翅にマーキングをおこない, 地図上に捕獲場所を記入し, ペテルセン法 (リンカーン法) を使って個体数推定をした (標識再補法) (今井・石井 (監修), 1998).
この方法は, 連続して2回の調査を行い, 1回目で捕獲した個体 (M個体: マーキング数) にマークして放し, 2回目に捕獲した際に捕獲個体 (n個体: 2回目の新規マーキング数+マーキング済みの捕獲数) 中のマーク虫 (m個体: マーキング済みの捕獲数) の比率から個体数 (N) を推定する方法である.
推定値 N=Mn/m
分散 V (N)=Mn (M–m)(n–m)/m3
推定値の95%信頼区間 N±1.96√V (N)
卵・幼虫の調査は, ギフチョウの食草であるカンアオイの葉の裏についている卵・幼虫の数を数え, 同時に測量図上に株と葉数・産卵数 (幼虫) を記録した.
併せて1998年と1999年に海上の森で行った調査と, 1996年の物見山自然観察会, 博覧会協会および愛知県が2000年より2003年まで行った万博アセスの準備書, 評価書, 2004年より行っているモニタリング調査報告書の調査結果とも比較検討した (表1).
結果及び考察
成虫飛翔調査
旧青少年公園におけるギフチョウ成虫の観察のピークは2001年には4月8日から22日, 全観察数は217個体, マーキングを51個体に行い, 再捕獲数は37個体であった (図2). 2002年は暖冬で桜の開花も早く, ギフチョウの初見日は3月30日と例年より1週間から10日ほど早かったが, その後天候が悪く低温だったため, ピークは4月5日と12日の2日あり, その間にはほとんど飛翔が見られなかった. 天候の不順のためか全体的に飛翔数は少なく全観察数85個体, マーキング個体19個体, 再捕獲数6個体とともに少なかった. 2003年では, 前年までの調査地域が文化財の発掘調査のために立ち入りができないために, 近接地に移動を余儀なくされた. 調査環境は同様な雑木林であったが, 全観察数は51個体と少なかったものの, マーキング個体22個体, 再捕獲数13個体は前年と比して多かった. 調査地が代わったことと, 発生日も4月7日から14日までと短かったため単純に比較はできないが, ギフチョウ成虫の飛翔個体は少なかったと思われる. 2004年は, 公園内に工事車両があふれるため, 危険であるという理由で立ち入り許可がでなかったために調査はできなかった. 2005年も万博開催中であるために調査許可は得られなかった. 博覧会協会でのモニタリング調査は2004年, 2005年も継続して行われている.
気象要因の飛翔への影響
調査期間中の気温と降水量, 日照時間を比較してみると
(表2), 1ヶ月の降水量は, 2001年は25.0 mmと少なく, 2002年は94.0 mm, 2003年は193.0 mmと観察個体数が減少しているのに対して降水量が増加をしており, 降水量も飛翔確認数に影響を与えたと思われる. 日照時間については, 2001年は218.5時間, 2002年は161.3時間, 2003年は136.0時間と降水量とは逆にギフチョウの飛翔を確認できた年に比例して長くなっている. 平均気温は, 2001年, 2002年, 2003年ともに15˚C前後と日照時間や降水量の違いによる大きな変化はみられず, また2001年と2003年では大きく飛翔確認数に違いがあるにもかかわらず, 平均的には同じであった. これはギフチョウが孵化した時に翅を乾かすためには, 天候が雨の日よりも晴れの日が多いほうが確実に多くのギフチョウの飛翔を確認することができると推測される. 実際にピーク時の15日間の天気の様子を比較してみると, 雨の日が2001年は2日しかなかったのに対し, 2003年は調査期間すべてで小雨が降るなど, 約3倍にもなった. 旧青少年公園では, 2003年は2002年4月より休園になったことから人の入り込みの影響がなく, 産卵数の急激な増加がみられた. 2003年より万博の造成工事が始まったため, 人の出入りによる成虫への影響や食草であるスズカカンアオイの分布の減少などにより成虫になれた個体が少なかったことなども考えられる. 調査日の気象条件により左右されることは経験により知られているが, その年の調査結果に大きく影響されることは考慮に入れられることは少ない.
2000年より博覧会協会は環境影響評価 (アセスメント) の調査を継続しておこなっており, 2000年, 2001年の調査結果が環境影響評価書に, 2002年, 2003年, 2004年はモニタリング調査がその報告書に書かれている (2005年日本国際博覧会協会, 2002, 2003–2005). 博覧会協会のアセスメントの調査では, 本研究と比べて個体数が非常に少なく (図3), 2000年には20個体, 2001年には23個体が観察されている. 単純に比較することはできないが, 比較データのある2001年でみると約1/9である. 本研究の調査結果から2001年の発生のピークは13日から22日まで続いたと思われるが, 博覧会協会では調査を4月5日から始めて14日で切り上げているため, 羽化のピーク前期で調査が終了したために少なかったと思われる. 2000年の調査も4月5日から始めているが, 12日に初めて目撃されたにもかかわらず14日には調査を終えている. このことは, 生物調査でありながら天候やその年の気候条件などを考慮して計画を立てる難しさを表す結果となった. 事業者が行うアセスメントにおいて調査結果だけで判断することが如何に危険であるか, 決められた予算で行うために臨機応変な対応ができないなどの欠点が浮き彫りにされるなど, 市民の地道な調査の必要性が改めて示される結果となった (八田, 1997). 新アセス法の手続きには, 市民からの意見書の提出が義務付けられており, 前述のような指摘をしたが2001年以降も調査日は変えられなかった. 2002年は天候に左右されたために, 本研究の調査結果では前年の2.5分の1と少なかったが, 博覧会協会の調査では前年の倍と増えている. しかし, 感覚的には決して発生数に大きな差があったとは感じられなかった. このようなことを考え合わせても, アセスメントにおいては少なくとも予備調査を含めて, 最低4, 5年は必要と考えられる (八田, 1998).
博覧会協会の目視調査 (主要な車道, 歩道等を踏査し, 確認位置を地図上に記録する方法) と本研究の調査 (標識再捕法) とは調査法や人員が違うので一概に比較はできないが, 博覧会協会の調査では2002年の公園閉鎖のために静かであった年 (観察個体46) よりも工事車両や人が沢山はいった2003年 (同76), 2004年 (同68) のほうが多く飛翔していたという皮肉な結果となっている. 前年の産卵が多かったためとも考えられるが, 2002年は本研究の調査では天候の不順で前年の半分にも満たなかった. 2002年では旧青少年公園は閉園されており, 一般の人の入り込みがなかったためにギフチョウの飛翔には影響がないと思われるが, 造成期間中の2003年と, 建築工事が行なわれている2004年には多くの人や工事車両が入っているにもかかわらず, ギフチョウの飛翔は多く見られた結果になっている. 2000年から2002年の調査では4月14日までに調査が終わっているが, 2003年では4月18日まで延長して行っているために, 観察された76個体のうち28個体が18日に観察されている. しかし, 2004年には4月12日で調査が終わっているにもかかわらず68匹が観察されている. 2003年には公園内の造成工事が始まり, 本研究の調査では2003年の産卵は前年の3分の1以下に減少しているが, 本研究の調査結果と違って博覧会協会の調査では飛翔も産卵も増加している.博覧会協会には調査法の改善を含めた申し入れを再三行ったが, 過去の調査結果との比較ができないとの理由で改善されなかった (前田, 2005).
これらの調査結果の違いをはっきりさせるためにも, 博覧会協会が行った目視法と本研究が行なった標識再捕法による個体数推定を行なった結果との検討が必要となろう.
標識再捕法による個体数推定
本研究ではペテルセン法 (リンカーン法) を使って個体数推定 (今井・石井 (監修), 1998) を行った結果, 2001年の観察個体185より推定個体は122から399 (平均260), 2002年は観察個体56より推定個体12から60 (36), 2003年では観察個体36より推定個体13から76 (44) となった.
成虫の飛翔数を比較すると博覧会協会の調査では2001年には23個体と本研究の確認個体の10分の1, 重複してカウントしたことも考慮してマーキングした数で比較しても51個体と半分以下であった. 本研究の調査が調査地の制限などで減少したことも考えられるが, 博覧会協会の調査が2003年, 2004年の工事期間中に2002年以前の調査の3倍にもなっていることは,調査の精度や熟練度を考慮しても私たちの調査結果と比較しても異常に多い結果となっている.
旧青少年公園は, 海上の森を遥かにしのぐ高密度の生息域であり, 広範囲にわたっている. 特に万博会場の南側(青少年公園開園時以前から残されている雑木林)と, 万博会場南部の周回道路周辺の林床部は東海地方では類を見ないほどの高密度である. 公園といった管理された利点と保護のしやすさから考えれば, まさにギフチョウの楽園とでも言えよう. 2004年の天候の不順 (発生前期の高温と中・後期の低温) の影響が心配されるが, 森林体感ゾーン内の改変によってスズカカンアオイの踏み荒らしと人や工事車両の影響がないことを前提とすれば, 工事期間 (2005年まで) の間に産卵地域及び産卵数を記録すればギフチョウの保護・保全に大きく貢献できるデータが蓄積されるであろう. ただし, 公園内でのギフチョウなど, 特定種の保全はホタルの保全 (放流) 事業と同じで, カンアオイなどの食草の移植は生態系保護とはならないことに注意しなければならない. 2003年の調査では調査地域内における文化財発掘調査(旧青少年公園内における成虫の高密度飛翔地域,ヒルトップ地域)により調査地域の変更を余儀なくされたため, 単純に比較はできないが発見個体は卵の調査結果から判断すると少なく, 2002年をも下回るが, 決して減っているとは思えない. 陸上性の昆虫, 特に飛翔性の高いチョウなどの成虫調査の困難さを浮き彫りにする結果となった.
スズカカンアオイ株数・葉数
スズカカンアオイの株数は海上の森では, 博覧会協会が行なった会場予定地が540 haから15 haに縮小する前 (1998年) の20647株が, 万博関連工事が始まる前の2001年では調査範囲が「会場およびその周辺(図1の海上の森の黒く塗りつぶされた地域)」と狭められたために792株に少なくなっている. その後2002年では2576株と大幅に増えており, その後も2003年2553株, 2004年2043株となっている. 同様に, 旧青少年公園も「評価書」の「注目すべき植物種の確認位置 (カンアオイ類)」では, 愛知青少年公園全体 (220 ha) であるのに対して2001年に3175株が確認されている. 2003年以降の「モニタリング調査報告書」では調査対象地域を公園全体ではなく(220ha),万博会場に使用された地域に (158 ha) に限定しているため, 調査面積が狭められているにもかかわらず2002年には5039株と大幅に増えている. その後2003年5238株, 2004年5389株とわずかに増加している. とくに, 環境影響評価書の直接改変域がスズカカンアオイの生育確認地をさけているかのごとく書かれているが,2003年以降の万博の造成工事により直接改変域(図1の愛知青少年公園の斜線部分)は完全に土壌表面が剥ぎ取られ, 2002年以前にギフチョウの産卵が確認されていたスズカカンアオイの群生地が大幅に無くなってしまったことを考慮するとさらにその増加は著しい (2005年日本国際博覧会協会, 2002, 2003–2005).
旧青少年公園の万博造成工事によって消失してしまったと考えられるスズカカンアオイの株は, 2003年の本研究の調査では, 測量して図面上に記録した株だけで1729株減少していた. 2003年にはキャンプ場の閉鎖や下草が刈られるなどして新たな群生地が見つかり, 2箇所で276株見つかった. しかし,2004年の造成工事によりその多くが消失したが, 2003年に新たに見つかった株は1株あたりの葉数が8.2枚と大きな株であった. この地点のひとつは今までキャンプ場であったためにスズカカンアオイは守られてきたが, 人の入り込みが多くギフチョウの産卵が少なかったために大きな株に育ったためと思われる. だが残念なことに, その後の万博会場施設の建設に伴う周辺整備によりほとんどが失われた.これらの調査結果の比較から見ても,前述の成虫の飛翔結果同様博覧会協会の調査結果には疑問が残る.
スズカカンアオイの株数と全葉数との調査は, 海上の森の1999年の調査 (広木ほか, 1999a) で1株当たり3.5枚であったのが, 2003年は1.9枚, 2004年は2.1枚と1株あたりの葉数が少なくなっている. それに対して旧青少年公園では2002年は4.3枚, 2003年は5.5枚と大株であった. 博覧会協会の調査結果がないために単純に比較はできないが, 本研究の調査では万博の造成工事により消失してしまったと考えられるスズカカンアオイの株数は2002年の調査で326株であった. しかし, 2003年には下草が刈られるなどして新たな群生地が見つかったために, 1株あたりの葉数がおおきくなったと思われる. 2004年は調査の許可が下りなかったために比較はできないが, 博覧会の調査結果では前年とスズカカンアオイの個体数がほぼ同じであることと, ギフチョウの飛翔数が約2倍に増えていることに加え, 産卵数も倍に増えていることから考えて, 食草の食いつぶしが起きることが予想される.
産卵株と無産卵株の比較
ギフチョウの産卵は幼虫のえさを確保するために大きな株にギフチョウのメスは産卵すると考えるのが妥当であると思われるが, 実際には1枚しか葉がない株であっても産卵しているケースが多く見られた. その産卵パターンに興味を覚え, 産卵している株 (有卵株) と産卵していない株 (無卵株) の葉の数を調査した. 旧青少年公園での2001年の有卵株は137株あり, 1株あたりの平均枚数は有卵株で3.6枚, 無卵株は4.9枚であった. 2002年においても, 1株あたりの平均枚数は有卵株4.6枚, 無卵株4.2枚であった. 2003年では, 1株あたりの平均枚数は有卵株5.5枚, 無卵株5.6枚と大きな差はなかった (図4). 産卵密度の低い地域, カンアオイの生息密度が低い地域を含むためばらつきが高いと思われる測量地以外の調査地点を含めた場合では, 2001年の1株あたりの平均枚数は有卵株10.2枚, 無卵株5.1枚であった. 2002年の1株あたりの平均枚数は有卵株2.2枚, 無卵株3.4枚と前年に比べて小さな株であった. 2003年の1株あたりの平均枚数は有卵株7.7枚, 無卵株5.0枚であった.群生地での有卵株と無卵株の差はほとんどなかったが, 調査地域全体では, 2001年, 2003年では有卵株のほうが大きな株であるという結果であった. キャンプ場などへの人の入り込みによるギフチョウ成虫の産卵が阻害されていたのが, 2003年の閉園に伴い, 大きな株が新たな産卵地域で見つかった. 全調査地域で2002年には幼虫の食いつぶしによる株の小型化が進んでいたが, 2003年では回復したと思われる.
この結果より, 産卵株の選択は株の大きさとは関係なく, 一般によく知られているカンアオイの新芽が展開するときに卵を産むタイミング説と合致し, ギフチョウの雌成虫は葉の枚数の多い少ないに関係なく, 産卵は最小枚数の1枚でも行われることが推測された. 卵から孵化したギフチョウ幼虫が食草であるスズカカンアオイを食べる様子を観察すると, 1卵塊にいた幼虫が一列に綺麗に並んで葉を食べている. このことから, ギフチョウの幼虫は特に生存のために, 過酷な生存競争をしないことがうかがえる. つまり, 幼虫が蛹になるまでに必要なスズカカンアオイの葉が無くなってしまうと, その株に寄生していた幼虫すべて餓死してしまう可能性が高く, 新しい葉を求めて移動するための危険率が上昇する. しかし, 雌成虫は観察結果からみても幼虫の摂食量などは考えずに新しい新芽に産卵するようであり, その地域の個体群を維持できるだけのスズカカンアオイが生育できる環境の保全が大切だと考えられる.
卵調査
海上の森におけるギフチョウは, 1996年の海上の森ネットワークによる調査 (海上の森ネットワーク, 1997) ではギフチョウ卵は海上の森全体で2733個観察されている. 調査面積, 人数等手法が違うために単純に比較はできないが, 1996年の調査時に1637個と多くの産卵が確認された3地点で行われた1998年の調査では54個, 1999年では57個と約50分の1にまで減少していた. このことは, 1998年, 1999年にボーリング調査や測量など,人やボーリングなどの騒音による影響があったためと, 海上の森が万博会場に決定したため全国から多数の採集者が押しかけて, ギフチョウの成虫及び卵の採集, スズカカンアオイの盗掘が影響したためと思われる (広木ほか, 2002). しかし, その後世界自然保護連合 (IUCN) や世界野生生物保護基金 (WWF) からの海上の森での万博開催に対する警告により, その開催地が旧青少年公園に移った. その後, 乱獲や人の入り込みが減少し, 海上の森全体で2002年では582個, 2003年で639個と1996年の約4分の1にまで回復してきている. しかし, スズカカンアオイが小さな株ばかりになり, 1株あたりの葉の枚数が2003年1.9枚, 2004年には2.1枚となり, 2004年は284個, 2005年の調査では199個にまで減少している.
1卵塊あたりの卵数は2001年には5月10日の調査時では幼虫が孵化し始めていたために正確な産卵数が確認できなかったが, 旧青少年公園の2002年では1卵隗の卵数6.8個に対して2001年7.3個とやや大きな数値が出たと思われる. 1999年に海上の森でおこなった調査では7.1個 (広木ほか, 1999b), 万博協会の青少年公園でおこなったアセスの結果とも2000年6.7個, 2001年6.5個と大差がない. 株数と葉数で比較してみると, 2003年の海上の森の1株あたりの葉数は約2枚となる. 2003年の旧青少年公園の1株あたりの葉数約5枚となる. 旧青少年公園の株は海上の森の株より大きい傾向にあると考えられる.
旧青少年公園では2001年は416個, 2002年は2106個, 2003年は653個であった. 2001年についてはまだ公園として一般の人が多く出入りしていたため産卵数は少なかったが, 海上の森から万博の開催地が青少年公園に移ったため, 青少年公園が2002年4月から休園となり, 一般の人の入り込みがなかった. そのために, ギフチョウの進入が多く, 多く産卵をすることが出来たためか, 約5倍の2106個もの産卵数を確認することができた. しかし, 2003年には再び産卵数は約3分の1にまで減少した. これは2003年より万博の造成工事が始まり, 多くその産卵数が確認されていた場所が無くなってしまったことや, 産卵が多く見られた場所で624個から30個と約21分の1にまで激減. 今まであまり産卵数が見られなかった場所で2003年には多くの産卵がみられるなど, カンアオイ群生地の減少によってギフチョウが追いやられている可能性が推察される.
カンアオイの分布と産卵密度
1996年の「海上の森ネットワーク」の調査結果で、海上の森全体で2733個の産卵が見られたうち, ほとんど見られなかった地域 (9個) での本研究の1999年の調査ではスズカカンアオイを670株観察したが, ギフチョウの卵は1個も確認することができなかった. しかし, 2002年にはこの地域で19卵塊117卵観察されたが, 2003年には286株953枚 (1株あたり3.33枚) 観察したにもかかわらず1卵も見つけられなかった. 2004年では879株, 1633枚 (1.85枚) 観察して, 3卵塊20卵を発見しただけである. これまでほとんど観察されたことがなかったこの地域で, 2001年, 2002年には成虫の飛翔が多く観察されている. ボーリングや測量調査に伴う立ち木, 下草の除去などにより林内の見通しがよくなったためにギフチョウの侵入が見られたためと思われる. しかし, 評価書に調査地域が特定されたためと思われるが, 前述のような採卵と盗掘の後が見られ, 大きな株のスズカカンアオイは見られなくなった. 旧青少年公園における2001年と2002年, 2003年の調査でも, 同様に産卵地域が移動している.
評価書に書かれている「スズカカンアオイの直接改変(造成工事および建設等) による影響」は旧青少年公園108箇所のうち7箇所と少なく, 卵塊数も2となっている. 同様に, 海上の森では, 16箇所のうち1箇所であるが, 「ギフチョウの生息環境及びスズカカンアオイの生息環境に変化が生じる可能性は否定できない」とされている. 現在万博の瀬戸会場として使われる地域には, スズカカンアオイが自生しているが, その後の周辺の開発により, 整備が進むとギフチョウが産卵にくることも考えられる. このことは, ギフチョウが里山の整備 (下草狩りなどの手入れなど) と関わっている所以でもあろう. ハッチョウトンボと同様, 里山を代表とする指標種は, 生息地の悪化を逃れて移動することにより生息を維持してきた. この連続性を断ち切ることは, ギフチョウの生息をも危機に陥れることになる.
スズカカンアオイが一度ギフチョウに摂食されると1年では完全にもとの状態, またはそれ以上に増えていくことが難しく, 実際に, ギフチョウに摂食された後の8月, 9月に同じ地域でのスズカカンアオイの葉数を調べてみると, 2003年の春は519枚から秋には158枚に減少しており, 2002年の春には1061枚から秋には436枚に減少し, 両年とも春から秋にかけて約3分の1にまで減少しているが, 2002年秋から2003年秋ではわずか83枚の増加だった(図5).全地域での総計でも2003年は2712枚が685枚に, 2002年は2038枚が546枚と, 約4分の1にまで減少している. 2002年, 2003年の調査結果では, 1年でスズカカンアオイは青少年公園全体では株で約1.5倍, 葉で1.8倍の増加をみせており, その分布や成長速度はさほど, おそくないように感じられるが, 前述のように新たに見つけられた地域も含むためである. 海上の森における1株あたりの葉数が非常に少ないのは, 卵の乱獲に伴い, 他地域では見られないスズカカンアオイを幼虫のえさのために大きな株ごと盗掘されたことも影響している. この結果はカンアオイ類の分布速度が非常に遅く, スズカカンアオイが一度ギフチョウに摂食されると, 1年では完全にもとの状態, またはそれ以上に増えることは難しい.この結果は, ギフチョウの住処が少なくなり特定のカンアオイ類と限定されてしまうなど, 食草であるスズカカンアオイもその摂食により絶滅しやすくなってしまう可能性があることを裏付けている. 大きな株になるのも自然では10年かかるとされており, ギフチョウの住処が少なくなり, 限定されてしまうと, 食草であるスズカカンアオイもその摂食により, 絶滅しやすくなってしまう可能性があることを裏づけている (大谷・広木, 1996).
博覧会協会の調査との比較
愛知万博を開催するに当たっての事業者である日本博覧会協会によるアセスメント調査結果のギフチョウの産卵数と本研究の調査結果とを経年比較してみると, 海上の森で1996年に2733個あったのが, 1998年54個, 1999年には57個と海上の森で万博が行われることが決まりボーリング調査やギフチョウの乱獲により壊滅的な状態になった. その後2002年は582個, 2003年には639個と回復したかに見えたが, アセスメントの評価書の発表後の2004年ではスズカカンアオイの大株の盗掘がおこなわれたと思われる地点では1卵も発見できなかった. その他の地域でも大幅に減少して2004年は284個, 2005年では199個だった. 博覧会協会の調査では種 (個体) 保護の観点から詳細な調査地域などのデータが公表されないため単純に比較することができないが, 博覧会協会の同じ年に行われた調査結果と比較してみると, 1999年は237個, 2000年では66個に減少し, 2001年には100個に回復し, 2002年には267個, 2003年は278個, 2004年は273個とその数は少しずつではあるが回復を示している (図6). 本研究での私たちの調査で激減した1998年以前の調査結果がないために, 博覧会決定以前のギフチョウの生息は数量的な比較ができないが, 江田などの記載によると1995年の調査では100頭を超える目撃があったとかかれている (江田ほか, 1999).
旧青少年公園では, 博覧会協会は2000年には518個, 2001年は1500個, 2002年は1285個あり, 2000年と2001年を比較すると, その数は約3倍となっており, また2002年より愛知青少年公園となり, ギフチョウにとっては一般の人の入り込みがなく, ゆっくりと産卵を行うことができたはずであるのに対して, 2001年の開園時よりも約215個減少している (図7). 調査結果を比較すると, 本研究の調査では2001年は調査面積が少なかったので416個と少ないが, 2002年の閉園時は2106個と博覧会協会の調査より821個多かった. 成虫の確認数をみると, 私たちの結果は2002年については2001年よりも成虫確認個体数は少なかったが, 愛知青少年公園休園のために, 落ち着いて産卵を行うことが出来たためか, 産卵数は多くなったと考えられる. 博覧会協会の調査では成虫確認個体数は回復しつつあるにもかかわらず, 215個産卵数が減少している. 2002年には愛知青少年公園が休園のため, 広範囲に産卵が行われたためとも考えられる. あるいは産卵場所の分布が変化したためと考えられる. 本研究の調査では2003年は造成工事が始まっていたために前年の半分 (653個) にまで減っていたが, 博覧会協会の調査結果では2003年, 2004年の造成工事とパビリオン等の建設工事期間中には2002年の閉園中の人の入り込みがなかった静かなときの約2倍 (2003年2185個, 2004年2451個) の産卵が報告されている.
自然保護への課題
なぜか万博の開幕に合わせて調査の精度が上がったのか, 旧青少年公園だけでなく海上の森での産卵数も増加している. 本研究の調査では海上の森では一時的に激減したものの, 万博が旧青少年公園へと移ったことで徐々に回復を見せている. これは海上の森では広範囲に生息環境が拡がっており, ギフチョウが生息することが出来る場所が散在していることがうかがえる. しかし, 旧青少年公園では海上の森のように広域でなく, 周りの開発が進んだ, 取り残された自然であるために, ギフチョウが分散できる場所が少なく, 今後万博終了後の解体・造成工事だけでなく, 万博開催中の多くの人の入り込みによる産卵への影響も考えられる.
この地域のギフチョウは特有な個体群である事が知られている (田中, 1996; Koda, 1996). この地域の個体群が公園化された「青少年公園」の中でいかに残ってきたかを解明することは, 今後のギフチョウの保護にとって大きなヒントとなろう.
更に, 土岐砂れき層を基盤とした東海固有の湿地や, 東海丘陵要素の特徴的な植物相を基盤としたハッチョウトンボやヒメタイコウチなどの特有な昆虫が多く見られるこの地域で, 「海上の森」のような多様性の高い里山に比べて, 公園化した「青少年公園」の中で細々と暮らしている湿地依存種の絶滅要件を乾燥などのぎりぎり状態を通して探ることができる. このことが将来予測される土地などの改変により必要とされる回避・低減・代償措置のあり方を考える基礎データとなろう.
謝 辞
本報を作成するにあたり, 南山大学の江田信豊教授, 愛知工業大学の内田臣一助教授をはじめ名古屋女子大学環境生物学ゼミに所属する学生, 長久手自然クラブ,海上の森を守る会,海上の森自然観察会を始めとした地域の自然保護団体の多くのかたがたに調査を手伝っていただきました. ここに記してお礼申し上げる. なお,本研究の一部は日本自然保護協会とWWF (世界野生生物保護基金) の助成金でおこなった.
引用文献
八田耕吉, 1997. 2005年愛知万博構想を検証する—里山自然の価値と「海上の森」: 58–63 (141pp.), (財) 日本自然保護協会, NACS-J保護委員会, 海上の森・万博問題小委員会.
———, 1998. 東海地方の里山の自然誌—万博アセス」に生態学的視野を. 科学68
(8): 620–627.
———, 2000. 昆虫から見た海上の森の生態系: 83–106(230pp.). 日本人の忘れもの, 名古屋リプリント.
広木詔三・江田信豊・八田耕吉, 1999a.
海上の森 (愛知県瀬戸市) におけるスズカカンアオイの分布パターンとギフチョウの産卵密度.
情報文化研究 (名古屋大学情報文化学部) 9: 23–30.
———, 1999b.
海上の森 (愛知県瀬戸市) の二次林におけるスズカカンアオイの個体群構造と1999年.
情報文化研究 (名古屋大学情報文化学部) 10: 37–48.
———, 2002. ギフチョウとスズカカンアオイ.
里山の生態学: 144–152.
名古屋大学出版会.
今井長兵衛・石井実 (監修), 1998. チョウの調べ方. 288 pp. 日本環境動物昆虫学会 (編), 文教出版.
海上の森ネットワーク, 1997. 96年度版瀬戸市海上の森調査報告書—自然環境から見た愛知万博基本構想の問題点.
45 pp. 海上の森ネットワーク.
Koda, N., 1996. Luehdorfia japonica: Current situation and
conservation satus in
江田信豊・広木詔三・八田耕吉, 1999. 里山環境における指標種ギフチョウ (Luehdorfia japonica) の生態学的調査—愛知県瀬戸市海上の森. アカデミア (南山大学紀要) 9:
1–9.
前田, 2005. 虚飾の愛知万博:109−117(239pp.),光文社.
大谷欣人・広木詔三, 1996. 静岡県富士川流域産スズカカンアオイで飼育した食草履歴の異なるギフチョウ個体群における幼虫の成長特性の差異.
昆虫と自然30 (13): 31–35.
田中 蕃, 1996. 愛知県豊田加茂広域圏のギフチョウ生息地.
日本産蝶類の衰亡と保護, 第4集.
やどりが (特別号): 39–48.
2005年日本国際博覧会協会, 2002. 2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価書.
1594 pp.
(財)
2005年日本国際博覧会協会.
———, 2003–2005. 2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価追跡調査 (予測・評価) 報告書 (その1)–(その5). 環境影響評価追跡調査 (モニタリング調査) 報告書 (平成14年度)–(平成16年度). (財) 2005年日本国際博覧会協会.
Summary
We have done the
investigation of the egg and the imago of Gifuchou (Luehdorfia japonica) in the development has been to
take place since 1998. An
investigation result in two places (
The peak of the observation of Gifuchou was one week of the
middle in April though at the
Gifuchou decreased to
2003 years which development construction began at even in 1/4 in (2001) though
217 were witnessed before it was decided that an international exposition was
held in the
Only 23 were witnessed by the investigation
which exposition society went for in the age of 2001 before it is decided that
an international exposition is held. But, it increases even in 3.3 times in
2003.
Because it was reduced in 15ha., Suzuka-Kan-aoi (Asarum kooyanum
Makino var. bachypodion
(F. Maek.) Kitam.) is 792 stock in the
evaluation document after it is decided as international exposition holding
(2001) that there was 20647 stock in the Kaisho
Forest in 1998.
But, it increases in more than 3 times after
2002 years why. Suzuka-Kan-aoi increase even in 1.6
times though 220ha was reduced in the same way in 158ha the Youth park
2733 number of laying of Gifutyou
in the
After that, it was cut by half in 2004 though it
was recovered even in 1/4 in 2002 years, 2003 years. But, though the number of
laying from 2002 has the influence of the construction with an investigation
zone's having become small, woods on the sea increase by the investigation of
the exposition society in the youth park from about 3 times to 5 times about 3
times.
A big difference for this research and the investigation of the exposition society, is probably a difference in the way of thinking toward the creature investigation. investigate way precision season change weather correspondence. Investigation such as an assessment of the environment is necessary including the spare investigation for 4-5 years.
Many butterflies
which a person didn’t go through for 2001 flew by our investigation, and many
laying were seen, too. But, there
were a few with 2003 when many people and cars for the construction came in
with butterflies and eggs. We are
afraid that an influence grows bigger during international exposition holding
in 2005.
青少年公園におけるギフチョウの観察のピークは2002年では例年より1週間ほど早かったが、4月の中旬の1週間であった。
ギフチョウが青少年公園で万博が催されることが決まる前(2001年)には217匹が目撃されたが、造成工事が始まった2003年には1/4にまで減少した。博覧会協会が行った調査では、2001年に23匹しか目撃されていなかったのが2003年には3.3倍にまで増えている。
スズカカンアオイは海上の森(540ha)で1998年には20647株あったのが、万博開催決定後15haに縮小されたために2001年の評価書には792株記録さている。しかし、2002年以降にはなぜか3倍以上に増えている。同様に、青少年公園も220haが158haに縮小されたにもかかわらずスズカカンアオイは1.6倍にまで増えている。
海上の森でのギフチョウの産卵数は博覧会開催が決まる前の1996年の調査では2733個観察されたが、開催が決定した翌年(1998年)以降は1/50にまで減少した。その後、2002年、2003年には1/4にまで回復したが、2004年には半減した。しかし、博覧会協会の調査では2002年からの産卵数は調査区域が小さくなったことと工事の影響があるにもかかわらず、海上の森が約3倍、と青少年公園で約3倍から5倍まで増えている。
本研究と博覧会協会の調査に大きな違いは、調査方法の精度と季節変動や天候などへの対応を含めた生物調査に対する考え方の違いであろう。環境アセスメントなどの調査は予備調査を含め4〜5年は必要である。
(Accepted September 3.2006)
[running
head]
left:
八田 耕吉・広木 詔三
right:
里山の指標となるギフチョウの保全
[Figure
legends]
図1. 調査地域図(「2005年日本国際博覧会環境影響評価書」などの図より修正・作図)
図2. ギフチョウ飛翔確認数.
図3. 年度別旧青少年公園ギフチョウ成虫飛翔確認数の比較.
図4. 有卵株と無卵株の葉の枚数平均 (旧青少年公園) .
図5. カンアオイ葉数春と秋の比較.
図6. ギフチョウ産卵数の比較 (海上の森).
図7. ギフチョウの産卵数 (旧青少年公園) の比較.
[Reprints] xxx copies with/without cover
表1. ギフチョウ成虫と産卵数.
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
海上の森 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(環境生物学ゼミ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成虫数 |
— |
|
— |
— |
|
|
— |
— |
— |
|
卵塊数 |
427 |
|
5 |
8 |
|
|
94 |
73 |
47 |
|
卵数 |
2733 |
|
54 |
57 |
|
|
582 |
639 |
284 |
|
平均卵数 |
6.4 |
|
10.8 |
7.1 |
|
|
6.2 |
7.8 |
6 |
|
(日本博覧会協会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成虫数 |
|
|
40 |
25 |
3 |
19 |
87 |
39 |
23 |
|
卵塊数 |
|
|
— |
38 |
10 |
16 |
39 |
47 |
42 |
|
卵数 |
|
|
— |
237 |
66 |
100 |
267 |
278 |
273 |
|
平均卵数 |
|
|
— |
6.2 |
6.6 |
6.3 |
6.8 |
5.9 |
6.5 |
|
旧青少年公園 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(環境生物学ゼミ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成虫数 |
|
|
|
|
|
217 |
85 |
51 |
|
|
卵塊数 |
|
|
|
|
|
67 |
335 |
128 |
|
|
卵数 |
|
|
|
|
|
416 |
2106 |
653 |
|
|
平均卵数 |
|
|
|
|
|
6.2 |
6.2 |
5.1 |
|
|
(日本博覧会協会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成虫数 |
|
|
|
|
20 |
23 |
46 |
76 |
68 |
|
卵塊数 |
|
|
|
|
77 |
230 |
195 |
327 |
399 |
|
卵数 |
|
|
|
|
518 |
1500 |
1285 |
2181 |
2451 |
|
平均卵数 |
|
|
|
|
6.7 |
6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.1 |
*平成8年 (1996) 広久手川流域 卵数503 (海上の森ネットワーク調べ).
表2. 調査期間中の平均気温・降水量・日照時間.
|
調査年度 |
平均気温 (˚C) |
降水量 (mm) |
日照時間 (h) |
成虫観察数 |
|
2001年 |
14.8 |
25 |
218.5 |
217 |
|
2002年 |
15.8 |
94 |
161.3 |
85 |
|
2003年 |
14.8 |
193 |
136 |
51 |
表3. スズカカンアオイ確認株数.(博覧会協会)
|
|
海上の森 |
|
青少年公園 |
|
|
調査年度 |
株数 |
(面積) |
株数 |
(面積) |
|
1998 |
20647 |
(540ha) |
|
|
|
1999 |
|
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
2001 |
792 |
(15ha) |
3175 |
(220ha) |
|
2002 |
2576 |
(15ha) |
5039 |
(158ha) |
|
2003 |
2553 |
(15ha) |
5238 |
(158ha) |
|
2004 |
2043 |
(15ha) |
5389 |
(158ha) |