動く書斎「しなの号」
237回。これは3年間に名古屋~長野間251.5㎞を旅した回数である。物好きに数えてみてびっくりするが、電卓をたたいて計算すると更に驚く。距離にすると約6万㎞、地球を1周半したことになる。時間にして約770時間、約1カ月間「しなの号」のなかに軟禁されたことになる。なお、出張なども含めて月平均3回帰宅したことになる。長野県西部地震のときに不通で東京を経由したことはあったが、さいわいにして、乗車してから遅延したことはなかった。その点ではJRさんを誇りに思っている。
たいていは、月曜日の名古屋8:00発「しなの3号」で長野に向かう。もちろん禁煙の9号車だ。3時間10分の長時間を、タバコの煙なしに過ごせるのはありがたい。私はグリ―ン車に乗るほどリッチではないので、このクリ―ン車を楽しんでいる。座席を選択するル―ルも体験から確立した。①中央の席ほど振り子電車に酔わない ②晴れの日は左側の方が直射が少ない ③横に柱のない窓際が落ち着く、という要素を考えて素早く選ぶ。同じ条件ならストレスを避けるため、大声で話す団体のおばさんや音楽を流す若者からは遠ざかるようにしている。また、一度座ったら終点まで立たない。盗難を防ぐことと他の乗客への配慮からである。そのため、乗る前にはトイレをすませ、飲物も飲まないようにしている。
観光案内の車内放送はこの列車の特長の一つだ。中乗りさんの由来などを交えた「木曾川」、よわい200歳を数える見返りの翁が深淵に釣り糸を垂れる「寝覚ノ床」、木曾義仲の旗上げの地、日義村の「徳音寺」、太平洋と日本海との分水嶺であり、ひばりより上にやすらう峠かな、と詠まれた「鳥居峠」、火山灰地からぶどう畑に変わった「桔梗ケ原」、楢山節考の舞台となった「姥捨」、善光寺平を帯のように流れる「千曲川」、などが紹介される。この他に木材の集散地「上松」や晴れた日には「御嶽山」「北アルプス」が加わることもある。変わったところでは、木曾節の一番を全部歌ってくれたことが1回だけある。正月の3日だったと思う。乗り合わせたご婦人から「今日の車掌さんは、何かいいことあったんじゃない?」という声も出たが、その日の車掌さんによって、事務的にやる人と心から楽しんでもらおうとする人との差が大きい。
JRさんもサ―ビスに気を遣ったり、車掌さんがオレンジカ―ドを売り歩いたり、努力の跡はみられるが、冷暖房だけはいけない。冬は暖かすぎるうえに、途中で喫煙車にあわせて換気するため寒くなるし、夏は夏で新聞の投書に出るぐらい冷房がきき過ぎる。我慢できず車掌さんに苦情を言っても「そうですかねえ」と反応がない。自分は背広にネクタイの盛装だから、半袖でノ―ネクタイの人の気持ちなど、ちっともわかってくれない。
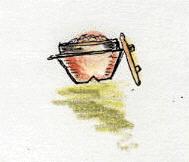
3時間の使い方もだんだんうまくなった。1年目は振り子に酔わないようにと、帰ってから元気が出るように、できるだけ眠った。行きは千種すぎの、帰りは塩尻すぎの検札を外すのが安眠のコツだ。それでも2時間も眠るのはなかなかの苦行で、ときどきは「岩魚の姿ずし」「塩尻の釜めし」「ワイン弁当」など魅力のある声に本能的に目覚めることがある。眠る合間に、行きは今週の予定を、帰りは土日の過ごし方や家族に言い置くことなどをとりとめもなく考えることが多い。当然ながら課員の飲酒運転事故から当分の間は、もっぱらそのことだけだった。
2年目になると振り子にも慣れて少し余裕ができた。まわりで本を読む人が多いので、おそるおそる活字の大きいものから挑戦してみたら結構いけた。今では文庫本まではいかないが新書本なら読めるようになった。もちろん目には良くない。その日のコンディションにより睡眠と読書のコンビネ―ションを考え、時間を有効に利用しているが、基本パタ―ンは自然にできあがった。
「しなの号」は、多少の揺れと騒音はあるが、美しい風景が次々に変わる窓を持ち、私にとっては貴重な第2の書斎である。北アルプスの山並みと犀川の流れがさわやかな初夏の松本、黄金色の稲が浮かぶ秋の田毎、綿帽子をかむった冬の寝覚ノ床、稲荷山駅の桜、どこかの駅の萩など、季節に合わせた風景を取り替えてくれる。1往復1冊を目標に本を読んでいるが、読み終わらないときは、もう少し乗っていたいと思うことがある。
3時間の乗車は長くてたまらないという人も多いが、お尻がペチャンコになることを除けば、今や私は苦にならない。だからといって、単身赴任をまだまだ続けろと言われると、やはり考え込んでしまう。名古屋へ向かうとき、岐阜県に入り「中津川」のアナウンスを耳にすると、反射的に娘の顔を思い出してしまうからである。