労働審判員の回顧
解雇や賃金未払いなど使用者と労働者間の労働事件を扱う、裁判に代わる新たな紛争解決方法として、4年前に「労働審判」制度が発足し、労働審判員を務めることになった。そして今年2月16日の労働審判を最後に、2期の任務を無事終えた。在任4年間を振り返ってみる。
担当事件数は通算24件(申立人総数は35名)。平均すると年6件だが、リーマン・ショックの影響もあり最終年度は11件と急増した。1件でも申立人が9名のときは、事前の準備も資料の持ち運びも大変だ。使用者の業種は、製造、販売、運送、建設、派遣、福祉など多岐にわたる。中小企業がほとんどで、会社名を知っていたのは3社だけ。申立人が外国人(中国、南米、西アフリカ)の場合もあり、代理人(弁護士)や同僚などの通訳を交えて進められた。
事件の多くは、解雇された労働者が復職や未払い賃金、慰謝料などを求めるケースで、解雇の経緯と態様は、使用者の横暴とか労働者のわがままなどが入り混じり、様々である。事前に提出された双方の主張と書証で概要は把握できるが、虚偽とか不利益な事実が隠されていたり、記憶違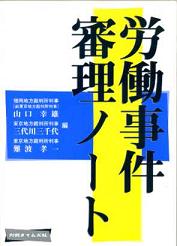 いがあったりする。審理は短時間なので的確に尋ねる必要がある。応答の表情や態度にも目を離せない。証拠不十分のため食い違ったまま終わる部分も残るが、審理が進むにつれて、どちらが優勢か見えてくる。双方の落ち度も浮かび上がる。続いて調停を試みる。労働審判では双方が早期解決を求めるので調停成立の可能性は高い(全国平均で約7割)。まず、審理で確認できた事実をもとに、審判官と使用者側・労働者側出身の労働審判員3名で協議し、申立内容について法的判断を下す。その見解を双方別々に説明し、これに基づき何度も双方に譲歩を促して解決を図る。
いがあったりする。審理は短時間なので的確に尋ねる必要がある。応答の表情や態度にも目を離せない。証拠不十分のため食い違ったまま終わる部分も残るが、審理が進むにつれて、どちらが優勢か見えてくる。双方の落ち度も浮かび上がる。続いて調停を試みる。労働審判では双方が早期解決を求めるので調停成立の可能性は高い(全国平均で約7割)。まず、審理で確認できた事実をもとに、審判官と使用者側・労働者側出身の労働審判員3名で協議し、申立内容について法的判断を下す。その見解を双方別々に説明し、これに基づき何度も双方に譲歩を促して解決を図る。
事件数の増加もあって初回での解決が増えつつあり、最終年度では半数を超えた。裁判所による事前の準備や当日の審判官(裁判官)の手際よさにもよる。だが、①代理人が初回で解決しようとする腹積もりがないとき②会社の代表者が出席していないとき③事件内容が複雑で追加調査が必要なとき④会社の組織が大きく決裁手続きに時間を要するときなどは即決ができない。
初回の解決でも、上限である3回目の解決でも、調停成立の瞬間はうれしい。審判官が主として進行するわけで自分が特に役立っていなくても、労務経験のある審判員として加わっているだけで調停案が説得力を増し、双方の歩み寄りを導いたとも思えてくる。初回で調停が行き詰まり、「審判」(判決に相当)で終結することもあった。その後、審判内容に基づいて当事者間で解決したのか、訴訟(裁判)に移ったのかは知らないが、虚しい気持ちが残る。
労働審判員の実務を通じて、リストラによる解雇、派遣切り、外国人労働者の増加など雇用状況の現実や、小企業の雇用実態に接することになった。家族的な雇用による雇用契約のあいまいさ、形ばかりの就業規則、退職手続きの不備、労働基準法を無視した発言など、ハラハラさせられる事象が少なくない。円満に過ごすうちはいいが、争いになると勝ち目は少ない。また、解雇された申立人が復職を申し出たケースでは、解雇無効の判断を得ても復職は実現せず、すべて金銭解決となった。裁判沙汰になると、労働者は使用者や職場の人たちとの信頼関係を失うことになるので、職場復帰は難しい。
最終日、名古屋地方裁判所へ通いなれた地下鉄桜通線「丸の内」のホームまで、地上から通算174段の階段を、思い出にふけりながら降りた。涙ながらに訴える「名ばかり管理職」の人、多忙な業務と職場のストレスからうつ病になって解雇された人、自分のポケットマネーから即日現金で解決金を支払った使用者、調停案は理解できるがこの申立人には時間外手当を支払わないと主張した使用者などの顔が浮かぶ。それぞれに事情がある。労働者は正義と生活をかけて訴え、経営者は信念と会社存続のために必死である。
昨年5月に裁判員制度がスタートし、刑事事件の裁判に一般市民が参加するようになった。「容易ではない任務だが、やればできる、やってよかった」という裁判員の感想がある。労働審判員としての私も同じだ。今年初めに、「最近の事件数の増加に対応するため」再任要請(来年4月から2年間)があった。今年4月から増員されても、まだ不足のようだ。高齢のため迷ったが、少しでもお役に立てればと内諾した。1年後に再登板できるよう、引き続き気力と体力の維持に心がけたい。
2010.3.3