ワインショップ・ワインバ-
ワインショップ、ワインバ-など、ワイン販売・消費の現場を見たり体験したりしました。
|
・ワインバ- L'ECLUSE(レクリュ-ズ)(フランス) 1995.9.18 |
・ローマのピッツァ~エノテカ (イタリア) 1996.9.17 |
|
・パリのワインショップ・ワインバ- (フランス)1999.10.21 |
・シェナのエノテカ (イタリア)1996.9.19 |
|
・ボルド-のワインショップ (フランス) 1999.10.16 |
・ワインの量り売り (ドイツ) 1995.9.25 |
ワインバ- L'ECLUSE(レクリュ-ズ)(パリ) 1995.9.18
14:25 近くにあるセ-ヌ川ぞいのワインバ-
L'ECLUSE(レクリュ-ズ)で、はしごをする。ボルド-専門のワインバ-で、パリに5店もあるという有名な店だ。グラスワインだけで28種類もある。しかも、それぞれ10clと15clの2種類ずつある。値段は10cl (100cc)で250円~800円ほどで、極めてリ-ズナブルだ。せっかくだからと、マルゴ-1989、ポイヤック1991、ポムロル1988、サンジュリアン1991など各地域産の銘酒を飲みくらべた。二人の場合は多種類の試飲ができていい。それぞれ熟成して本当においしく、甲乙つけがたい。もう一つの発見は、カマンベ-ル・チ-ズとスライス・リンゴの取り合わせだ。チ-ズの脂肪とリンゴの酸味とのバランスが絶妙で、赤ワイン好きの人に是非すすめたい。小さな店だが上質だ。店員さんと写真を撮ってからメニュ-をいただけないかとお願いしたら、快くくださった。ますますこの店が好きになった。
パリのワインショップ・ワインバ- 1999.10.21
14:40 やっとパリでのフリ-タイムとなる。まず、ここから歩いても遠くないフランス銀行そばのワイン店
Legrand Filles et Fils(ルグラン・フィ-ユ・エ・フィス) に向かう。この店のワインのストックは2000種類もあるそうだが、店内の品揃えは多くない。店のフランス人らしい女性は、流暢な日本語で電話の応対をしている。昨今は日本も本格的なワインブ-ムで、日本人との取引も多くなっているのだろう。店を見るだけで出た。次はガイドブックに「パリのワイン・バ-の元祖」と記された
Willi's Wine Bar(ウイリ-ズ・ワイン・バー)。近くに2店あるが、15:30古い方のいわば1号店へ入った。壁にはワインに関するコミカルなポスターが店全体にずっと張ってある。空いていたのでカウンタ-に座り、グラスワイン (11cl) を注文した。白は南仏の銘酒 Condrieu(コンドリュ-) '97 (65F=1240円)で、深いコクがある。赤はボルド-のサンテミリオン'95(54F=1030円) で、これも飲み応えがあった。メニュ-にはグラスワインが何種類も用意されていた。そのなかにアルゼンチン、オーストラリアなど「新世界ワイン」も含まれている。女性店員の応対は極めて無愛想で惜しまれる。次はマドレ-ヌ広場を目指す。ここは比較的わかりやすく、迷わずに行けた。最初の店は
Fauchon(フォ-ション)。名古屋の「丸栄」地下にも出店しているのでブランドはおなじみだが、ここには様々な食品がある。「16,000種類もの高級商品が常時そろっている」そうだ。お菓子売り場を一通り見てから、地下のワイン売り場へ進んだ。ボルド-やブルゴ-ニュの超高級ワインから中級ワインまである。見ているうちに高級ではないワイン1本をつい買ってしまった。試飲コーナーもある。通りを渡って別館に入る。ここにはチーズ、ソ-セ-ジ、野菜、果物などの食材やデリカテッセンが並んでいる。パリ在住の人の書物にしばしば登場する店だ。次にワインのチェ-ン店 Nicolas(ニコラ)も店内を一巡する。パリに 360軒もこのチェ-ン店があるそうだ。ここにも試飲コーナーが設けられている。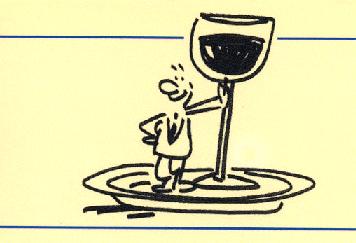
17:30ワインバ-
l'Ecluse(レクリュ-ズ)に入る。この店はボルド-ワインを専門にしていて、高級グラスワインの種類が多いことでもよく知られている。パリに4店あり、4年前にセ-ヌ河岸店に初めて入ってすっかり気に入ったので、今回ぜひ別の店にも行ってみたかったのだ。ワインリストを見ると、何と'75年産のが2種類あった。小さい方のグラス (10cl) でサンテミリオン(66F=1250円) と Haut-Medoc(オ-メドック)産 (85F=1620円) を迷わず注文した。おつまみはタルタル(牛赤身の生肉)にポテト、生野菜添え。見た目はピンク色のハンバ-グという感じで、とろりとした舌触りがいい。ワインはともに熟成が進み、れんが色で、ボルド-らしいタンニンの渋みが薄れ、穏やかで複雑な味わいがした。とにかく得がたい古酒だった。店のメニューをほしいとお願いしたら、無料でいただけた。ぜひまた来たい店だ。17:45 店を出る頃は満員になっていた。レクリュ-ズの料理メニュ-にはユーモラスなイラストがいくつも描かれているが、表紙の吹き出しに
"SUSHI"の文字を見つけた。イラストはカップルが寿司をとり、さらに白ワインをオ-ダ-する場面で、ワイン名の一部 "SANS-SOUCIS"と "SUSHI"の韻を踏んだおもしろさもある。なかを開くと特別メニューに寿司がある。仏語の辞書を頼りに記載内容を再現してみると、およそ次のようになる。「東洋の伝統とダイエットを好む方に、これまでにない大きな喜びを味わっていただくために厳選した、極上の11切れの盛り合わせ
"sushi de Paris 99F" をご用意しました。火曜日の昼と木・金曜日の夕の特別サービスで、鮮度保証。初めての方も、リピ-タ-も、夜のパ-ティ-の予約もどうぞ。11切れの内訳は、マグロ 1、 サーモン 1、 ヒラメ 1、 ボラ 1、 omelette japonaise (卵焼き) 1、日本でもワインが日常生活に定着しはじめ、最近は寿司や天ぷらなど和食とも合わせるようになってきたが、本場のワイン・バ-にまで日本食が進出したとは喜ばしい限りだ。フランスの料理における健康志向の強さを示すものでもある。
ボルド-のワインショップ(フランス) 1999.10.16
お目当ては大劇場近くに集中する三つのワイン店。この7月にボルド-周辺を旅した若いワイン通の友人から、Eメ-ルで「わざわざ行く価値のある店」と薦められた名所だ。まず、
La Vinotheque de Bordeaux(ラ・ヴィノテ-ク・ド・ボルド-) 。9:00 開店。当然ながら著名なワインがずらりと並ぶ。有名シャト-の名前が入ったワインの木箱の板を張り合わせてドア-板にしている。シャンデリアはブドウの枝と房のデザインだ。グラスやデキャンタ-などが飾られた展示台が回転している。次は Bordeaux Magnum(ボルド-・マグナム) 。店全体の展示がわかりやすく、洗練されている。ワイングッズが充実していて、日本ではまだ見たことがないシャンパン用のラピッド・アイス(ボトルの側面を囲って急冷する帯状のもの) を買った。赤、白、ソ-テルヌワイン入りのジャムまである。もう一つは L'Intendant(ランタンダン)。この店はユニ-クだ。入ったときは狭く品数が少ないと思ったが、そうではなかった。実は中央が5階までらせん階段でつながっており、円形の各階の壁面は本棚のように細かく仕切られ、無数のワインが整然と陳列されている。例えば毎年違う有名画家の描いたラベルが美しいシャト-・ム-トン・ロ-トシルトは'94,'95,'96と縦に並べてあり、価格差もわかりやすい。この3年ほどの暴騰はすさまじく、ここでも1本2万円以上するので拝観するのみだ。3店とも、確かに「わざわざ行く価値のある店」だった。
ローマのピッツァ~エノテカ(イタリア) 1996.9.17
21:00 すぐ近くのスペイン広場へ行った。『ロ-マの休日』のスペイン階段には、夜も若者たちが、通り道もないほどに座り込んで話し合っている。背後のトリニタ・ディ・モンティ教会の二つの鐘楼が、うまく借景になっている。手前の「小舟の噴水」がやわらかくライトアップされ、きれいだ。22時、雑誌『フィガロ』に紹介されていたエノテカ
(ワインバ-) ENOTECA ANTICA DI VIA DELLA CROCEに入る。ここはグラスワインを手頃な値段で楽しめる。トスカ-ナ地方の赤ワイン Chianti(キアンティ:4000リラ=310円) 、高級な Brunello di Montalcino(ブルネッロ・ディ・モンタルチ-ノ:8000リラ=620円)、ブドウの絞り滓から作った甘く強い酒「ヴィン・サント」を試した。ビ-ルもある大衆的な店で、よくはやり、みんなよくしゃべる。日本人の会話のように間が空かず、二重唱や三重唱のように双方が同時に違う言葉を話しているようだ。店の女性に「グラッパ(ブドウの絞りかすから造られた蒸留酒) は?」と勧められたが、思いとどまり席を立った。ホテルには23時すぎについた。万歩計を見ると、今朝から4万歩寸前だ。
シェナのエノテカ(イタリア:トスカーナ地方) 1996.9.19
22:15 意気揚々とエノテカへ行った。このエノテカは城壁の「メディチの要塞」内にあり、常設では国内唯一の国立エノテカだ。イタリアは世界一のワイン産出国で、この地下には国内の774種類のワインが地方別にぎっしり展示されており、有料の試飲と販売をしている。二人で赤ワインBrunello di Montalcino
(ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ)、Vino Nobile di Montepulciano(ヴィ-ノ・ノ-ビレ・ディ・モンテプルチア-ノ)、Amarone(アマローネ)を試す。前の二つは最高格付けの DOCG(統制保証原産地呼称) ワインだ。DOCG はイタリア中で14銘柄が指定されている(うちトスカ-ナ州は5銘柄)。カウンタ-を離れて飲む。古いレンガ造りのベランダに立ち、夜城壁を眺めてワイングラスを傾けるのはいいものだ。幾種類もの良いワインを、素朴な雰囲気で、安く気軽に飲めるのはいい。こういう店が名古屋城にでもあれば、きっと通いつめてしまう。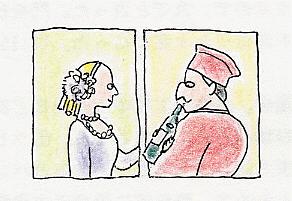
別の部屋に、ワインに関するユ-モアあふれるイラストが何点も飾られている。ボトルの赤ワインを絵筆につけてワインボトルの絵を描くもの、2本のボトルの底の盛り上がったくぼみを乳房に見立てたもの、名画のパロディ-でモナリザがワインのことを思い浮かべているもの、ウルビ-ノ公
(ウフィツィ美術館所蔵)の鉤鼻にワインボトルを近づけたものなどがあり、思わずクスッと笑ってしまう。23:00 1本ぶら下げてホテルへ戻った。
ワインの量り売り(ドイツ:チュービンゲン) 1995.9.25

ブドウの絵や「梅酒」の文字にひかれて店をのぞく。いくつも積まれた樽の蛇口の一つをひねり、ワインをグラスに注ぐ人がいる。私たちも試飲をしてみようかと思ったが、もう少し観察してからにする。樽も見えずに、手洗い場のように蛇口だけ六つ並んだコーナーもある。ここでも女性が一人で次々飲みくらべている。よく見るとフランスの赤ワインが多い。客の女性は、店の人と話しながら何度も試飲したうえで銘柄を決め、別のコーナーから空瓶を持ってきて、自分で蛇口から瓶に注ぐ。いっぱいになるとコルク栓を挿入する道具を使って、慣れた手つきで栓をする。あとはレジで勘定をするだけだ。要するに、ワインの量り売りをする店で、このような店があることさえ知らなかった。ドイツワインの新酒もある。店全体を見まわすと、量り売りは、ウィスキー、シュナップス
(いわばドイツの焼酎) からオリーブオイルやゴマ油まである。地下蔵のような装飾もしてあり、いい店だ。サイトマップ