 豊臣秀次生誕地(愛知県あま市)
豊臣秀次生誕地(愛知県あま市) 愛知県あま市乙之子屋敷21に貴船社があります。
この神社の案内板には次のように記されています。
「長尾武蔵守豊臣吉房入道三位法印一路」これが豊臣秀次の父親の名前です。 この三位法印が実の息子である豊臣秀次の関白就任を祝し、さらに武運長久をを祈願するために自分の屋敷の近くにこの貴船社を建立したということなのです。三位法印屋敷跡は侍屋敷と呼ばれ、この貴船社の北にあったようですが、もう少し北西の愛知県あま市篠田三分寺にあったのではないかという説もあるそうです。三分寺には歩道の片隅に小さな「参府寺之碑」が建っています。 豊臣秀次の父親の屋敷が愛知県あま市(旧美和町)にあったのだから、当然豊臣秀次はここで生まれたのだろうと考えるわけですが、豊臣秀次の生誕地は、ここ愛知県あま市という説と名古屋市緑区大高町という説があります。大高町という説は江戸時代に書かれた尾張藩の記録『尾張志』に見られます。 『尾張志』海東郡の「宅跡」のページに「三位法印宅」として次のように記されているのです。
三位法印は豊臣秀吉の姉「とも」と結婚した後大高に移り住んで豊臣秀次を生んだと書いてあるのですが、大高にはそれを裏付ける記録や伝承などがなく、やはり秀次は三位法印屋敷で生まれたと考えるのが妥当なんだそうです。とはいえ、ウィキペディアには「尾張知多郡大高村で生まれた」と紹介されているんですけどね。 それにしても、『尾張志』での三位法印の評価、低いですね。 生誕地巡りに戻るのはこちらです。 |
 貴船社 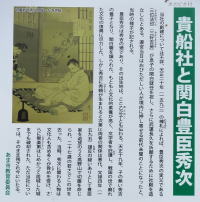 貴船社案内板  参府寺之碑 |







 豊臣秀次は秀吉の甥であり、その出生地は、ここ乙之子とも伝わる。天正19年、子の無い秀吉の養子となり、関白職を譲られた。もともと文化的要素が高く、文学者を庇護し、戦国の世で廃れた文化の復興に尽力した。しかし、秀吉に秀頼が生まれると、次第に両者の関係は悪化、文禄4年(1595)謀反の疑いありとして豊臣家を追放のうえ高野山で切腹を命じられ、27歳の若さでこの世をった。当時秀吉に関わる人物は文化人も含め多くが咎めを受け、さらに聚楽第はじめかつて居城した城までも破却された。ただ当社については、そのまま残され今にいたる。
豊臣秀次は秀吉の甥であり、その出生地は、ここ乙之子とも伝わる。天正19年、子の無い秀吉の養子となり、関白職を譲られた。もともと文化的要素が高く、文学者を庇護し、戦国の世で廃れた文化の復興に尽力した。しかし、秀吉に秀頼が生まれると、次第に両者の関係は悪化、文禄4年(1595)謀反の疑いありとして豊臣家を追放のうえ高野山で切腹を命じられ、27歳の若さでこの世をった。当時秀吉に関わる人物は文化人も含め多くが咎めを受け、さらに聚楽第はじめかつて居城した城までも破却された。ただ当社については、そのまま残され今にいたる。